News ニュース
| May 26 2025 | Mr. Ratthaphong Phumphu, Ton, successfuly finished his PhD defense talk at Khon Kaen University in May. As an examiner, I visited there and shared wonderful hours with friends in Thailand.

|
| March 3 2025 | We get an AMED grant for promoting an international collaboration between Japan (PI, Dr. Iwama; co-PI, Sashida) and France. Our proposal is to understand roles of non-canonical PRC2 in normal and malignant hematopoiesis. |
| February 20 2025 | I hosted the last international symposium for our core-to-core program: Integrative approach for normal and malignant hematopoiesis. For its contents, please refer to those pages. |
| more |
Research 研究
正常および白血病幹細胞の制御機構の理解:骨髄異形成症候群(MDS)は、無効造血、血球異形成および急性骨髄性白血病(AML)への移行を特徴とする造血幹細胞のクローン性疾患、難治性の血液がんです。MDS細胞は表現型および遺伝子型において不均一であり、MDS発症の機序は完全には解明されていません。過去十数年のがんゲノムシークエンス解析によって、MDSやAML患者において、エピゲノム制御因子やRNAスプラシング因子を含めた様々な体細胞変異(一部胚細胞変異もある)が同定されました。興味深いことに、約10年前に、血液がん患者に頻繁に認められたエピゲノム制御因子(DNMT3A、TET2、ASXL1など)の変異は、健常高齢者の多くの血液細胞でも起きていることが報告されました。その後、相次いで同様の知見が報告され、現在はクローン造血として知られます。実際、老化は血液がんを含む様々ながんのリスクを高めることが知られており、クローン造血(ゲノム変異)に加えて、環境因子や細胞・組織へのストレスによるエピゲノム変化ががんの発症要因と考えられます。従って、造血幹細胞へのエピゲノム変化の蓄積によって、クローン造血・前MDS幹細胞から、MDSの発症と病態進展に至ると推測されます。ただし、エピゲノム変化は様々な階層(塩基、クロマチン、染色体、核内領域)で起こり得るために、がん幹細胞のおける本態や相互作用は明白ではありません。
こうした血液がん研究の状況の下、私たちの研究室では、包括的な研究手法(遺伝子改変マウス、ゲノム編集、ATAC-seqやChromosome conformation captureなどの網羅的なシークエンス解析など)を活用しています。エピゲノム変化が正常な造血幹細胞をどのように損ない、血液がんを発症するのか、その分子機序を解明するために、クロマチンと染色体動態に焦点を当てて取り組んでいます。現在の正常造血および悪性造血に関する研究課題は下の通りです:
課題1) 染色体・クロマチン動態変化による血液がん幹細胞の発生と拡大の機序解明
私・指田吾郎は、2009年からシンシナティ小児病院と千葉大学において、MLL1変異体の分子メカニズムを解明しました(Zhang Y, Blood 2012; Tanaka S, Blood 2012)。 千葉大学の岩間研究室では、高齢者のクローン性造血や血液がんにおいて頻繁に変異するスプライシング因子SF3B1の幹細胞制御機構を初めて報告しました(Wang C, Blood 2014)。 さらに、エピゲノム制御因子の機能喪失による血液がんの病態基盤を解明するために、造血器腫瘍で頻繁に変異するEZH2およびTET2遺伝子の遺伝子改変マウスを用いて、複数のMDSモデルを確立しました (Muto T, J Exp Med 2013; Sashida G, Nature Commun 2014; Mochizuki-Kashio M, Blood 2015)。2014年12月から熊本大学で私の研究室を開き、クロマチン動態とエンハンサー機能不全に焦点を当てて、骨髄系腫瘍および希少白血病の病態基盤を解明しました (Sashida G, J Exp Med 2016; Wang C, J Clin Invest 2018; Kubota S, Nature Commun 2019; Yokomizo-Nakano T, Cancer Res 2020; Bai J, Oncogene 2021; Morii M, Leukemia 2024)。引き続き、私たちは、様々な要因によるクロマチン動態の変容によって正常な造血幹細胞をどのように損なわれて血液がんを発症するのか、その分子機序を解明していきます。
また、私たちは、トリソミー8やトリソミー21(ダウン症)などのトリソミーの生物学にも取り組んでおり、数的染色体異常が幹細胞機能にどのように影響して、造血や神経などの様々な組織における疾患の発症機構を研究しています。ダウン症を一例として、老化造血細胞と他臓器との相互作用から、がんや臓器不全などの老化関連疾患の発症の仕組みの理解を目指しています。
課題2)環境要因・細胞外因子依存的な血液がん発症の機序解明
私たちは、MLL転座白血病やRUNX1-ETO白血病マウスモデル(Abdallah MG, et al. Leukemia 2021)など、いくつかの白血病遺伝子誘導モデルを構築して、年齢依存的ながん発症の分子機構を研究しています。さらに、細菌とウイルス由来産物による刺激の後のTet2遺伝子欠損マウスモデルを作製して、MDS発症が促進することを見出しました。その機序として、造血幹細胞において非標準的な自然免疫応答であるTlr3/4-Trif-Polo-like-kinase経路が、Elf1転写因子を活性化し、クロマチンを再構築しMDS発症を促進することを報告しました(Yokomizo-Nakano T, J Exp Med 2023)。また、クロマチン制御因子であるHmga2は胎児造血幹細胞で高発現し、幹細胞遺伝子の転写を活性化しています。炎症ストレス下で、造血幹細胞がHmga2発現と機能を活性化することで、速やかに造血幹細胞自体と造血が再生される分子機序を解明しました(Kubota S, EMBO J 2024)。この仕組みは、ヒトがん遺伝子発現データの解析から、血液がん幹細胞でも機能していることが推測されました。このように、私たちは、感染や炎症などの環境要因によるクロマチン変化が、血液がんの発症をどのように促進するかを解明して、難治性血液がんであるMDSなどに対する新たな標的法の概念を実証していきます。
略歴
指田吾郎は1996年に東京医科大学医学部を卒業。その後、東京医科大学血液内科の大屋敷博士の指導のもと、2002年に博士号を取得。2005年、ポスドク研究員として、米国ニューヨークのメモリアルスローン・ケタリングキャンサーセンターのNimer博士の研究室に渡米し、ELF転写因子の機能を研究。2009年、シンシナティ小児病院のHuang博士の研究室に移り、白血病のエピゲノム研究を開始した。2010年11月に帰国して、千葉大学の岩間厚志博士の研究室に移籍。2014年12月、熊本大学国際先端医学研究機構に自身の白血病転写制御研究室を開き、2016年12月に教授に昇進。
Members 研究メンバー

E-mail: sashida-gr

TEL:
Members
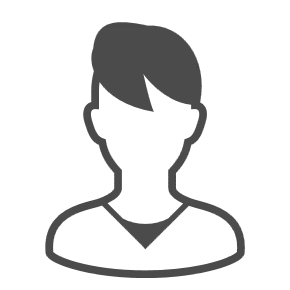
MS: Reseach support associate/Lab manager



MD: PhD student (D3, Kumamoto University)

MD: PhD student (D3, Kumamoto University)

MD: PhD student (D2, Kumamoto University)
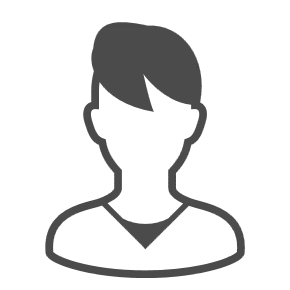
BS: PhD student (M1, Kumamoto University)
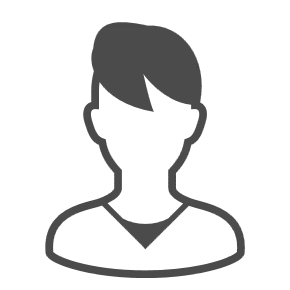
DDS: part-time Reseach assistant
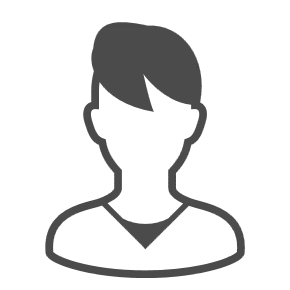
MD, PhD: Visiting Professor
Alumni:
At Kumamoto University from December 2014 to March 2025
- Sara Kaneda: part-time research assistant/MD student (-2016)
- Takako Ideue, MD: Research Specialist (-2018)
- Daiki Tanaka, MD: part-time research assistant/MD student (-2019)
- Gaber Abdallah Abdallah, MD: Visiting research fellow (-2020)
- Nanami Kurita: part-time research assistant/MD student (-2020)
- Kuan Jew Win, MD, PhD: Research fellow (JSPS-RONPAKU, PhD from Kumamoto University) (2017-2020) (Current position; Professor, University of Malaysia, Sarawak)
- Supannika Sorin, BS: Visiting PhD student (2020-2021)
- Ayaka Maeda, MD: part-time research assistant/MD student (-2021)
- Wang Yongjie: PhD student (2020-2022)
- Yonoshin Hayashi: part-time research assistant/MD student (-2022)
- Takako Yokomizo, PhD: Post-doctoral researcher (2015-2022) (Current position; Asistant Professor, The University of Tokyo)
- Yuqi Sun, MD, PhD: PhD student (PhD from Kumamoto University) (2017-2022)
- Sho Kubota, PhD: Asistant Professor (2015-2023) (Current position; Asistant Professor, Okayama University)
- Ratthaphong Phumphu, BS: Visiting PhD student
- Mariko Morii, PhD: Post-doctoral researcher (JSPS-RPD) (-2024) (Current position; Asistant Professor, Okayama University)
- Jie Bai, PhD: Post-doctoral researcher (2015-2024) (Current position; Post-doctoral Researcher, UT San Antonio)
- Mayumi Hirayama, DDS, PhD: Post-doctoral researcher (2022-2025)
- Mihoko Iimori, MT: Reseach assistant/Lab manager (2015-2025)
Achievement 研究業績
Selected research articles:
- Kubota S, Sun Y, Morii M, Bai J, Ideue T, Hirayama M, Sorin S, Eerdunduleng, Yokomizo-Nakano T, Osato M, Hamashima A, Iimori M, Araki K, Umemoto T, Sashida G*. EMBO Chromatin modifier Hmga2 promotes adult hematopoietic stem cell function and blood regeneration in stress conditions. EMBO J 2024; 43(13): 2661-2684.
- Morii M, Kubota S, Iimori M, Yokomizo-Nakano T, Hamashima A, Bai J, Nishimura A, Tasaki M, Ando Y, Araki K, Sashida G*. TIF1β activates leukemic transcriptional program in HSCs and promotes BCR::ABL1-induced myeloid leukemia. Leukemia 2024; 38(6): 1275-1286.
- Yokomizo-Nakano T, Hamashima A, Kubota S, Bai J, Sorin S, Sun Y, Kikuchi K, Iimori M, Morii M, Kanai A, Iwama A, Huang G, Kurotaki D, Takizawa H, Matsui H, Sashida G*. Exposure to microbial products followed by loss of Tet2 promotes myelodysplastic syndrome via remodeling HSCs. J Exp Med 2023; 220(7): e20220962.
- Kawano S, Araki K, Bai J, Furukawa I, Tateishi K, Yoshinobu K, Usuki S, Nimmo RA, Kaname T, Yoshihara M, Takahashi S, Sashida G*, Araki M*. A gain-of-function mutation in micro-RNA-142 is sufficient to cause the development of T-cell leukemia in mice. Cancer Sci 2023. 114(7): 2821-2834.
- Umemoto T, Johansson A, Ahmad SAI, Hashimoto M, Kubota S, Kikuchi K, Odaka H, Era T, Kurotaki D, Sashida G, Suda T*. ATP citrate lyase controls hematopoietic stem cell fate and supports bone marrow regeneration. EMBO J 2022. 41(8): e109463.
- Abdallah MG, Niibori-Nambu A, Morii M, Yokomizo T, Yokomizo T, Ideue T, Kubota S, Teoh VSI, Mok MMH, Wang CQ, Omar AA, Tokunaga K, Iwanaga E, Matsuoka M, Asou N, Nakagata N, Araki K, AboElenin M, Madboly SH, Sashida G*, Osato M*. RUNX1-ETO (RUNX1-RUNX1T1) induces myeloid leukemia in mice in an age-dependent manner. Leukemia 2021. 35(10): 2983-2988.
- Bai J, Yokomizo-Nakano T, Kubota S, Sun Y, Kanai A, Iimori M, Harada H, Iwama A, Sashida G*. Overexpression of Hmga2 activates Igf2bp2 and remodles transcriptional program of Tet2-deficient stem cells in myeloid transformation. Oncogene 2021; 40(8): 1531-1541.
- Shide K, Kameda T, Kamiunten A, Ozono Y, Tahira Y, Yokomizo-Nakano T, Kubota S, Ono M, Ikeda K, Sekine M, Akizuki K, Nakamura K, Hidaka T, Kubuki Y, Iwakiri H, Hasuike S, Nagata K, Sashida G, Shimoda K*. Calreticulin haploinsufficiency augments stem cell activity and is required for onset of myeloproliferative neoplasms. Blood 2020; 136(1): 106-118.
- Yokomizo-Nakano T, Kubota S, Bai J, Hamashima A, Morii M, Sun Y, Katagiri S, Iimori M, Kanai A, Tanaka D, Oshima M, Harada Y, Ohyashiki K, Iwama A, Harada H, Osato M, Sashida G*. Overexpression of RUNX3 represses RUNX1 to drive transformation of myelodysplastic syndrome. Cancer Res 2020; 80(12): 2523-2536.
- Kubota S, Tokunaga K, Umezu T, Yokomizo-Nakano T, Sun Y, Oshima M, Tan KT, Yang H, Kanai A, Iwanaga E, Asou N, Maeda T, Nakagata N, Iwama A, Ohyashiki K, Osato M*, Sashida G*. Lineage-specific RUNX2 super-enhancer activates MYC and promotes the development of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm. Nature Commun 2019; 10: 1653.
- Wang C, Oshima M, Sato D, Matsui H, Kubota S, Aoyama K, Nakajima-Takagi Y, Koide S, Matsubayashi J, Mochizuki-Kashio M, Nakano-Yokomizo T, Bai J, Nagao T, Kanai A, Iwama A*, Sashida G*. Ezh2 loss propagates hypermethylation at T-cell differentiation-regulating genes to promote leukemic transformation. J Clin Invest 2018; 128(9): 3872-3886.
- Sashida G*, Wang C, Tomioka T, Oshima M, Aoyama K, Kanai A, Mochizuki-Kashio M, Harada H, Shimoda K, Iwama A*. The loss of Ezh2 drives the pathogenesis of myelofibrosis and sensitizes tumor-initiating cells to bromodomain inhibition. J Exp Med 2016; 213(8): 1459-1477.
- Mochizuki-Kashio M, Aoyama K, Sashida G, Oshima M, Tomioka T, Muto T, Wang C, Iwama A*. Ezh2 loss in hematopoietic stem cells predisposes mice to develop heterogeneous malignancies in an Ezh1-depenedent manner. Blood 2015; 126(10): 1172-83.
- Wang C, Sashida G, Saraya A, Ishiga R, Koide S, Oshima M, Isono K, Koseki H, Iwama A*. Depletion of Sf3b1 impairs proliferative capacity of hematopoietic stem cells but is not sufficient to induce myelodysplasia. Blood 2014; 123(21): 3336-43.
- Sashida G*, Harada H, Matsui H, Oshima M, Yui M, Harada Y, Tanaka S, Mochizuki-Kashio M, Wang C, Saraya A, Muto T, Hayashi Y, Suzuki K, Nakajima H, Inaba T, Koseki H, Huang G, Kitamura T, Iwama A*. Ezh2 loss promotes development of myelodysplastic syndrome but attenuates its predisposition to leukaemic transformation. Nature Commun 2014; 5: 4177.
- Muto T#, Sashida G#, Oshima M#, Wendt GR, Mochizuki-Kashio M, Nagata Y, Sanada M, Miyagi S, Saraya A, Kamio A, Nagae G, Nakaseko C, Yokote K, Shimoda K, Koseki H, Suzuki Y, Sugano S, Aburatani H, Ogawa S, Iwama A*. Concurrent loss of Ezh2 and Tet2 cooperates in the pathogenesis of myelodysplastic disorders. J Exp Med 2013; 210(12): 2627-39. #equal contribution
- Tanaka S, Miyagi S, Sashida G, Chiba T, Yuan J, Mochizuki-Kashio M, Suzuki Y, Sugano S, Nakaseko C, Yokote K, Koseki H, Iwama A*. Ezh2 augments leukemogenicity by reinforcing differentiation blockage in acute myeloid leukemia. Blood 2012; 120(5): 1107-17.
- Zhang Y#, Yan X#, Sashida G#, Zhao X, Rao Y, Goyama S, Whitman SP, Zorko N, Bernot K, Conway RM, Witte D, Wang QF, Tenen DG, Xiao Z, Marcucci G, Mulloy JC, Grimes HL, Caligiuri MA, Huang G*. Stress hematopoiesis reveals abnormal control of self-renewal, lineage bias, and myeloid differentiation in Mll partial tandem duplication (Mll-PTD) hematopoietic stem/progenitor cells. Blood 2012; 120(5): 1118-29. #equal contribution
- Sashida G, Bae N, Di Giandomenico S, Asai T, Gurvich N, Bazzoli E, Liu Y, Huang G, Zhao X, Menendez S, Nimer SD*. The Mef/Elf4 transcription factor finetunes the DNA damage response. Cancer Res 2011; 71(14): 4857-65.
- Sashida G, Liu Y, Elf S, Miyata Y, Ohyashiki K, Izumi M, Menendez S, Nimer SD*. ELF4/MEF activates MDM2 expression and blocks oncogene-induced p16 activation to promote transformation. Mol Cell Biol 2009; 29(13): 3687-99.
Selected reviews:
- Yokomizo-Nakano T, Sashida G*. Two faces of RUNX3 in myeloid transformation. Exp Hematol 2021; 97: 14-20.
- Sashida G, Oshima M, Iwama A*. Deregulated Polycomb functions in myeloproliferative neoplasms. Int J Hematol 2019; 110(2): 170-178.
- Sashida G*, Iwama A*. Multifaceted role of the polycomb-group gene EZH2 in hematological malignancies. Int J Hematol 2017; 105(1): 23-30.
- Sashida G, Iwama A*. Epigenetic regulation of hematopoiesis. Int J Hematol 2012; 96(4): 405-12.
- Ohyashiki JH*, Sashida G, Tauchi T, Ohyashiki K. Telomeres and telomerase in hematologic neoplasia. Oncogene 2002; 21: 680-687.
Guest editor:
- Sashida G*. Recent advance in MDS research. Exp Hematol 2024. Comments on Cammenga, Exp Hematol 2024; Nishimura K, et al. Exp Hematol 2024; Xu JJ, Viny AD, Exp Hematol 2024; Merz AMA, Platzbecker U. Exp Hematol 2024.
- Sashida G*. Stem cell regulation and dynamics in myeloid malignancies. Int J Hematol 2023 Jun;117(6):789-790. Comments on Fang Y-C, et al. Int J Hematol 2023; Hayashi Y, et al. Int J Hematol 2023; Jin Z, et al. Int J Hematol 2023; Abdallah MG, et al. Int J Hematol 2023.
Grant 助成金
Selected Grants from Japan Society for the Promotion of Science (JSPS):
- Grants-in-Aid for Scientific Research (C) (2011-2013); Principal Investigator, 5,070,000 Yen
- Grants-in-Aid for Scientific Research (C) (2014-2016); Principal Investigator, 4,810,000 Yen
- Grants-in-Aid for Scientific Research (B) (2016-2018); Principal Investigator, 18,590,000 Yen
- Grants-in-Aid for Scientific Research (B) (2018-2020); Principal Investigator, 17,290,000 Yen
- Grants-in-Aid for Challenging Research (Pioneering) (2019-2020); Principal Investigator, 6,500,000 Yen
- Grants-in-Aid for Scientific Research (B) (2021-2023); Principal Investigator, 17,420,000 Yen
- Grants-in-Aid for Challenging Research (Pioneering) (2021-2022); Principal Investigator, 6,500,000 Yen
- Core-to-Core Program Advanced Research Network; Integrative approach for normal and leukemic stem cells (2020-2024); Coordinator, 72,765,000 Yen
- Grants-in-Aid for Scientific Research (B) (2024-2026); Principal Investigator, 18,460,000 Yen
Grants from Japan Agency for Medical Research and Development (AMED):
- P-PROMOTE (2022-2024); Principal Investigator
- Integrated Neuroscience Program (2024-2026); Co-Principal Investigator (PI, Dr. Nariko Arimura)
- ASPIRE (2025-2029); Co-Principal Investigator (PI, Dr. Atsushi Iwama)
Education 教育
Supervised Theses:
- Kuan Jew Win, MD, PhD; PhD from Kumamoto University (2017-2020): Low prevalence of the BCR-ABL1 fusion gene in a normal population in southern Sarawak. Kuan JW, Su AT, Tay SP, Fong IL, Kubota S, Su'ut L, Osato M, Sashida G. Int J Hematol. 2020; 111(2): 217-224.
- Supannika Sorin, MS; MS from Khon Kaen University (2021): Sorin S, Kubota S, Hamidi S, Yokomizo-Nakano T, Vaeteewoottacharn K, Wongkham S, Waraasawapati S, Pairojkul C, Bai J, Morii M, Sheng G, Sawanyawisuth K, Sashida G. HMGN3 represses transcription of epithelial regulators to promote migration of cholangiocarcinoma in a SNAI2-dependent manner. FASEB J. 2022. 36(7): e22345.
- Yuqi Sun, MD, PhD; PhD from Kumamoto University (2017-2022): The acidic domain of Hmga2 and the domain's linker region are critical for driving self-renewal of hematopoietic stem cell. Sun Y, Kubota S, Iimori M, Hamashima A, Murakami H, Bai J, Morii M, Yokomizo-Nakano T, Osato M, Araki K, Sashida G. Int J Hematol. 2022; 115(4): 553-562.
- Ai Hamashima, MS; MS from Kumamoto University (2023-2024): Bone marrow transplantation induced a distinct transcriptional profile in HSC from that in primary aged mice.
Internship Students:
- Ullah Md. Emdad (January 2017, from Bangladesh)
- Tabassum Rahman Sunfi (January 2019, from Bangladesh)
- Aizhan Baltabay (October 2019, from Kazakhstan)
- Arusyak Ivanyan (September 2022, from Armenia)
- Teona Paresishvili (November 2023, from Georgia)
- Abdalla Essam Mohamed (January 2025, from Egypt)
人材募集・問い合わせ
研究室秘書:
2026年4月から勤務ができる研究室秘書の方を探しています。ご興味のある方は、sashida-gr(at)igakuken.or.jp まで連絡をください。
研究補佐員・ラボマネージャー:
2026年4月以降から、勤務ができる研究補佐員の方を探しています。ご興味のある方はsashida-gr(at)igakuken.or.jpまで連絡をください。
大学院生・訪問研究者・ポスドク研究者:
ストレス造血、血液がん、臓器連関に関する研究に興味のある方、質問がある方は、sashidag(at)kumamoto-u.ac.jp または sashida-gr(at)igakuken.or.jp まで連絡してください。博士号取得を目指す学部性、大学院生、意欲的なPhD研究者、基礎研究に興味のある臨床医など、さまざまな方からの連絡を常時待っています。