このページを印刷
未来を話そう!
プロジェクト研究の紹介
うつ病プロジェクト
いまだ不明なうつ病の病態に迫り、客観的診断法の確立や新しい治療法の開発を目指します

WHO(世界保健機関)が「2030年には最も多くの人々を苦しませる病気になる」と警告するうつ病ですが、その正確な病態はいまだによくわかっていません。
ヒト死後脳やモデル動物、オリゴデンドロサイトを中心とした細胞レベルのモデル系の解析を用いた研究を通して、副作用の少ない、より効果的な根本治療法の開発に挑むラボをご紹介します。
うつ病プロジェクト
楯林 義孝 プロジェクトリーダーが解説します。
Yoshitaka TATEBAYASHI
Project Leader
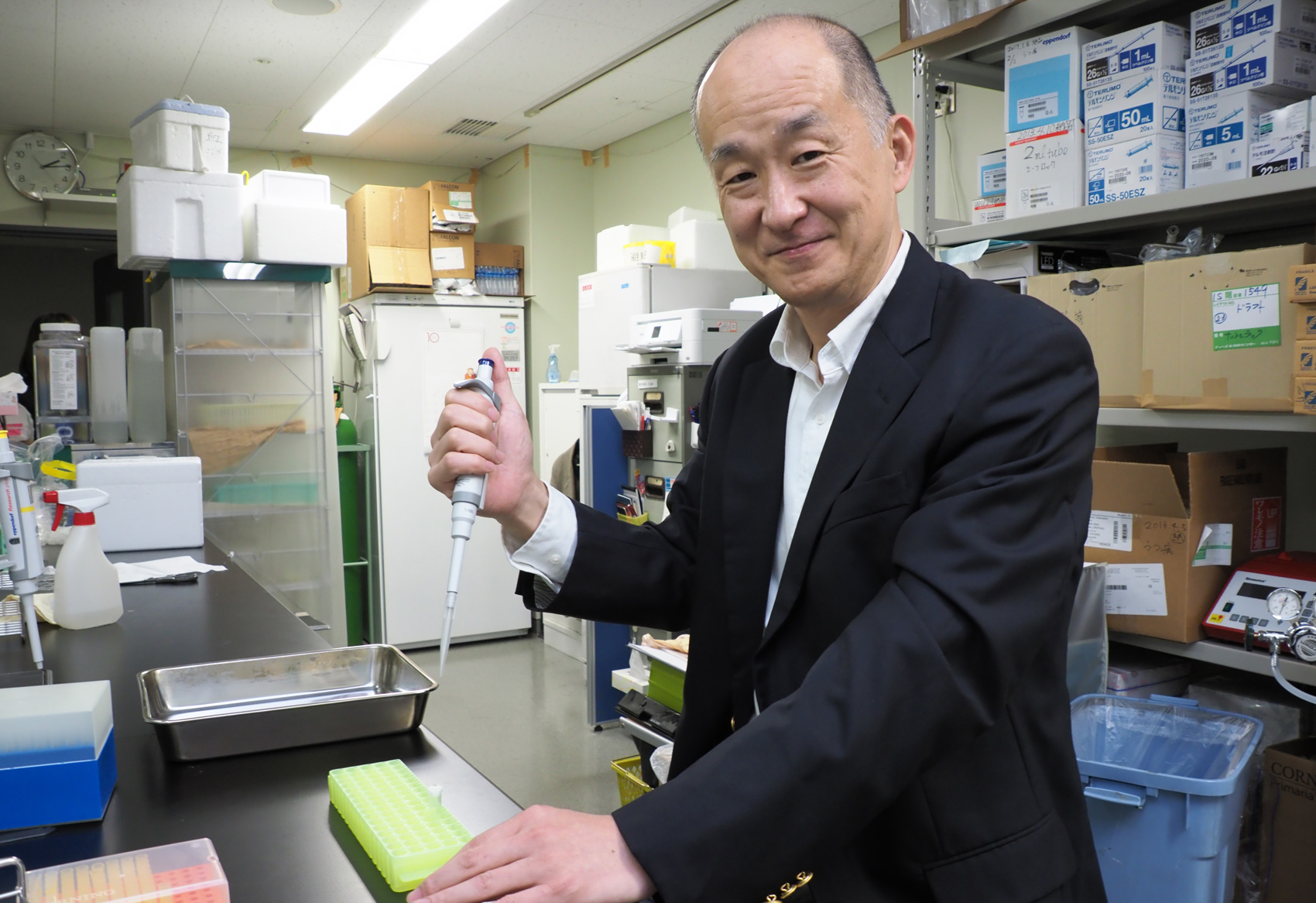
うつ病プロジェクト
楯林 義孝 プロジェクトリーダーが解説します。
Yoshitaka TATEBAYASHI
Project Leader
どんなことに役立つの?
現在、うつ病の発症メカニズムは一部しか明らかになっておらず、十分とはいえません。本研究を通してうつ病患者の脳で異常が起こっている部位やその病態を正確に探り当てることができれば、画像解析や血液検査といった客観的診断法の確立や、より効果的で副作用の少ない治療法の実現につながります。
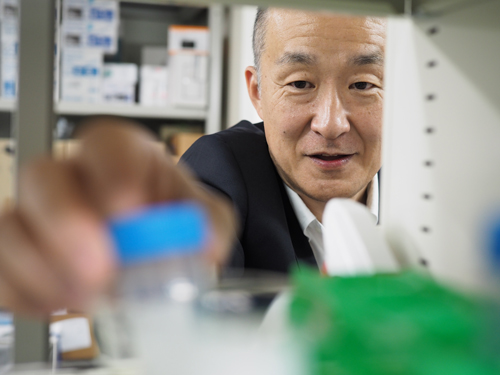
研究の社会的背景
うつ病による社会的損失額は年間2兆円にも!
—— うつ病は個人や社会にどのような影響を及ぼしますか?
楯林うつ病になることで本人やそのご家族が苦しみ、失業などの社会的機能低下につながるだけでなく、最悪の場合は自殺に至るおそれもあります。また、社会的損失額の大きさも問題で、医療費など、直接的なものだけを見積もっても年間2兆円ほどになります。ご家族や職場など、周辺への影響も含めれば、そのインパクトは計り知れません。
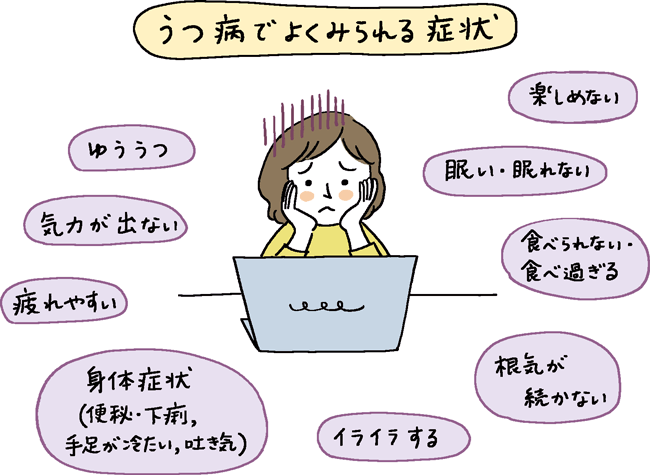
—— 現在の治療薬にはどのような限界があるのでしょうか?
楯林現在、薬物治療の主流となっているのはSSRIやSNRIという薬ですが、これらの薬のおおもととなるイミプラミンという薬は、1950年代に偶然に発見されたものです。これらの薬がうつ病に効くメカニズムは相当研究されてきましたが、薬の作用メカニズムだけでうつ病をすべて説明することはいまだにできていないのです。実際、最近の薬は副作用も少なくなり処方数も増加してきましたが、これらの薬で治療の効果がみられるのが全体の約7割、本当の意味での寛解* まで導けるのは全体の3~4割にすぎないともいわれています。効果がみられない患者さんも約3割程度いるという意味では、治療薬としては不完全で、研究の余地が残っているわけです。
*寛解:
完治とは言えないまでも、症状が治まり落ち着いた状態を保っていること。
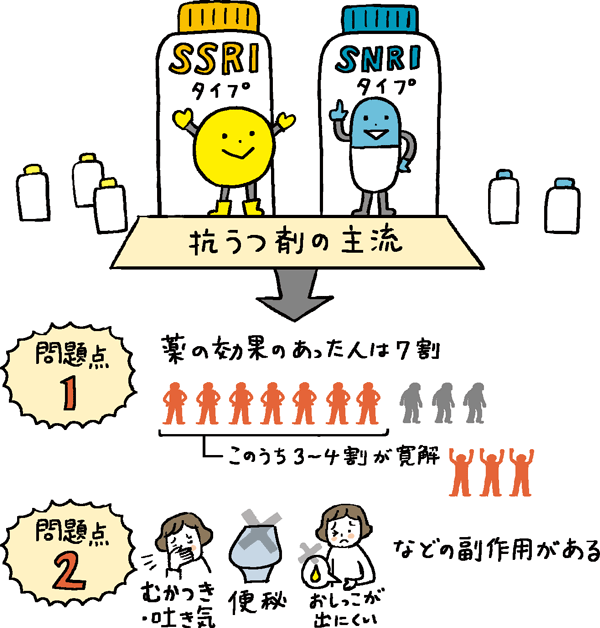
また、副作用は、①むかつき・吐き気、②便秘、③おしっこが出にくい、の順(個人差有り)で認められる。
具体的な研究手法
キーワードは「グリア細胞」
—— ラボではどのような研究を手がけているのですか?
楯林柱の一つとなるのがうつ病モデル動物を用いた研究で、ストレスを受けたラットが脳細胞にどのような影響を受けるか詳しく調べています。マウスと比べて社会性の高い動物であるラットを複数匹、1つのケージでしばらく生活させることで、弱い個体が強い個体からストレスを受ける状態を作るイメージですね。
ストレスを受けたラットに抗うつ薬を投与すると、認知機能や睡眠については改善が見られるものの、あまり効果が見られない脳の部分もあります。それはラットの脳の中でも人の爪の先ほどくらいしかない小さな部位で、人間では前頭葉に当たるところです。うつ病患者の前頭葉では、現在の抗うつ薬の効果が出づらいことが次第に明らかになっています。
—— これまでの研究で、どのようなことが明らかになったのでしょうか?
楯林前頭葉に着目した研究を通してわかってきたのが、ストレスにより変化が目立つのが「グリア細胞」であるということです。グリア細胞は、その語源がグルー(英語で接着剤の意)であることからもわかるとおり、以前は脳の神経回路を「くっつける」働きをするだけと思われてきました。
私たちの研究で、うつ病患者の死後に、その脳を調べてみたところ、前頭前野でグリア細胞が減少していることがわかりました。そこで私たちは、特にうつ病に関係が深いと思われるオリゴデンドロサイトというグリア細胞に焦点を合わせ、脳細胞レベルのモデル系の確立とその機能の解明に挑んでいます。解明できていないことが山ほどあるからこそ、一つひとつ地道に解明していくことが、よりよい治療の足がかりとなるのです。
未来への展望
うつ病とアルツハイマー病の意外な関連性とは?
—— 認知症にも関わりがある研究だそうですね。
楯林認知症の約7~8割を占めるアルツハイマー病の、最大の危険因子の一つはうつ病です。つまり、うつ病はアルツハイマー病の発症と深い関係があることが近年の欧米の疫学研究からわかってきています。グリア細胞に注目したまったく新しい研究を進めることから、うつ病との関連性が明確になり、アルツハイマー病の治療にも貢献することが期待できるのではないかと考えています。
—— これからのうつ病治療における展望を教えてください。
楯林現在では低い寛解率しか望めないうつ病治療の可能性を切りひらき、予防や根治まで視野に入るようになれば人類にとって大きな福音です。そのためには、よりよい治療薬の開発はもちろんのこと、客観的診断法を確立することも重要です。うつ病リスクのある人へ的確な予防策を講じ、発症したとしても早期に効果的な治療を受けられるような時代へ向けて、前進していきたいと思います。

客観的診断法の確立で、
災害時のうつ病への効果的な治療にも期待が集まる!
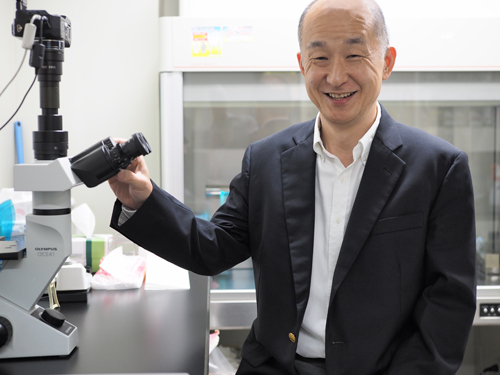
現在、うつ病の診断は問診が中心となることが多く、画像解析や血液検査などを用いた簡便で有効な客観的診断法には研究の余地が多く残されています。ストレスにより体内で起こる変化が血液検査などで客観的にわかれば、患者の状態に応じた的確な治療に寄与することは確実です。
客観的診断法の確立は、災害時のうつ病の迅速な診断・治療につながることも期待できます。たとえば、東日本大震災では、長期にわたる避難所生活などが原因でうつ病に罹患した人が少なくありませんでした。災害時には、想定外の事態に強いストレスを受けた高齢者がうつ病になったり認知症が進行したりすることで、若い世代の負担も増えるという悪循環が懸念されます。災害対策の一つとしても、私たちの研究の意義は大きいと信じています。