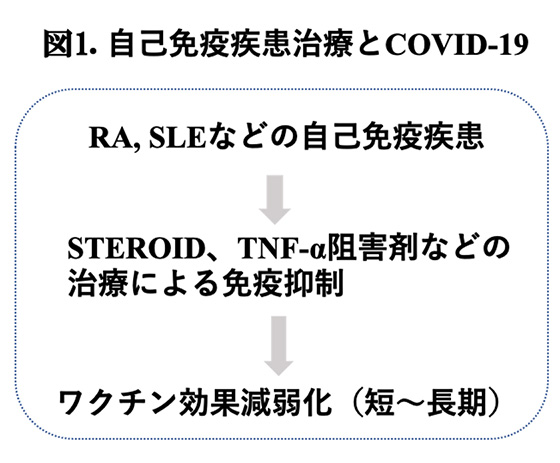※世界各国で行われている研究成果をご紹介しています。研究成果に対する評価や意見は執筆者の意見です。
一般向け
研究者向け
2023/1/17
自己免疫疾患における新型コロナワクチン効果の持続性
文責:橋本 款
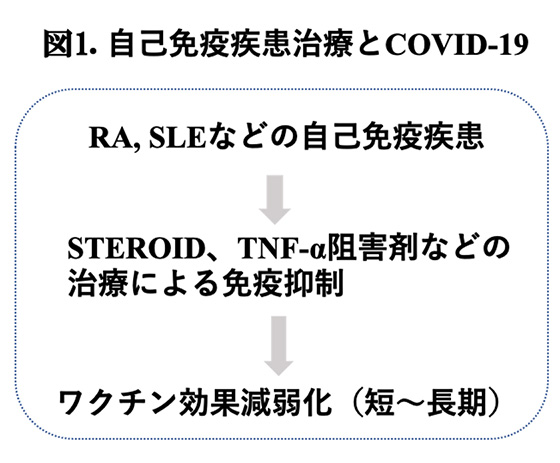
関節リウマチ(RA)や全身性エリテマトーデス(SLE)などの膠原病は、本来、自分を守ってくれる免疫細胞が誤って自分自身の組織を攻撃してしまう「自己免疫疾患」*1の病気です。これらの病気の治療には、慢性的な免疫・炎症を抑える目的で、ステロイドやその他の生物学的製剤を継続的に使わざるを得ず、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)などの感染症に対して特別な配慮が必要になります。これに関連して、免疫抑制剤によるワクチンの減弱効果は重要な問題です(図1)。実際、これまで免疫抑制治療がmRNAワクチンを弱めるという報告はありましたが、多くの報告は2回目接種後3ヶ月以内のワクチン効果が最大となる時点での評価であり、その後の持続性については、その臨床的な重要性に関わらず、報告されていませんでした。これに対して、大阪大学の研究グループは自己免疫疾患(膠原病)患者のCOVID-19に対するmRNAワクチン接種後の免疫動態を解析し、ステロイドだけでなく、いくつかの免疫抑制治療でウイルスに対する中和抗体価が長期的に見ると減弱することを発見し、その結果を米国科学誌「The Lancet Regional Health - Western Pacific」に発表しましたので、今回は、この論文(文献1)について解説致します。
文献1.
Yamaguchi Y et al., Persistence of SARS-CoV-2 neutralizing antibodies and anti-Omicron IgG induced by BNT162b2 mRNA vaccine in patients with autoimmune inflammatory rheumatic disease: an explanatory study in Japan, The Lancet Regional Health - Western Pacific Published: December 19, 2022
【背景・目的】
自己免疫疾患の患者ではCOVID-19による重症化のリスクが健常者に比べて高いことが報告されており、ワクチンによる感染・重症化予防が重要である。しかしながら、自己免疫疾患に対して使用される免疫抑制治療にはワクチンによる免疫反応を減弱させる懸念があるため、本研究においては、どのような治療がワクチン効果に影響するかを明らかにすることを目的とした。
【方法】
本前向きコホート研究*2では、大阪大学医学部附属病院免疫内科に通院中の患者さんより血液サンプルを収集し(2021年2月1日~2022年2月28日)、これらのサンプルを用いて、ワクチン接種前後の新型コロナウイルスに対する中和抗体価の変化やオミクロン株に対する抗原特異的な液性免疫・細胞性免疫の解析を行なった。患者さんの内訳は、自己免疫性リウマチ疾患;439例(RA n=190, SLE n=76, その他)、健常者;146例であった。
【結果】
- ステロイドやアバタセプト*3による治療を受けている患者さんではピークの中和抗体価が早期に(14-42日)減弱し、その後の中和抗体価も低いことがわかった。
- また、TNF-α阻害薬を使用している患者さんではピークの中和抗体価は健常者と変わらないものの、その後の中和抗体価の維持が長期的に(100-200日)減弱することがわかった。
- オミクロン株に対する抗原特異的抗体価およびT細胞応答の評価では、抗原特異的抗体価は野生型の中和抗体価と強い相関関係にあったが、中和抗体価が低い患者さんでもT細胞応答は検出されており、液性免疫があまり得られない治療を受けている患者さんでもワクチン接種を行う意義があると思われた。
【結論】
本研究により、ステロイドやアバタセプトでは早期に、TNF-α阻害薬での治療を受けている患者さんでは長期的にmRNAワクチンによる免疫反応が減弱するという知見が得られた。十分な感染予防効果を維持するためにはワクチンを繰り返し接種することが望ましいとされているが、加えて、患者さんごとの特徴に応じてワクチン投与方針を考えることが重要であると考えられた。
用語の解説
- *1. 自己免疫疾患
- 細菌やウイルス、腫瘍などの自己と異なる異物を排除するための役割を持つ免疫系が、本来の働きをせずに自分自身の正常な細胞や組織に対してまで過剰に反応し攻撃を加えてしまうことで異常を来す疾患の総称である。自己免疫疾患の原因は、明らかにされていないが、体内のタンパク質が変質して異物として認識されてしまうケース、タンパク質の構造が似ているため誤って攻撃してしまうケース、免疫機能そのものに何らかの障害が起きているケースなどが考えられている。自己免疫疾患は、膠原病をはじめとする全身の臓器に症状が現れるものと、潰瘍性大腸炎やネフローゼ症候群(肝臓の病気)といった臓器特異的な自己免疫疾患に分けられる。自己免疫疾患には多くの病気があるが、特効薬となるような治療薬はない。
- *2. 前向きコホート研究
- 疾病の要因と発症の関連を調べるための観察的研究の手法の一つである。要因対照研究、前向き研究(prospective study)ともいわれる。特定の疾病要因に関わっている(例:ウイルスが感染する可能性の環境にいた)集団と、無関係の集団の2グループを作り、それぞれのグループの中での対象疾病発生率を算出することで、要因と疾患発症の関連性を調べることができる。前向きコホート研究によるメリット・デメリットは、それぞれ以下のようなものが挙げられる。
〔メリット〕
- 疾患発症に至るまでの発生順序を解明できる。
- 複数の事象、原因を知ることができる。
- 研究者側のバイアスがかかりにくいため、間違った結果を導くことが少ない。
〔デメリット〕
- 発生率の低い疾病研究には向いていない。
- 研究にかかる費用と時間が膨大である。
- *3. アバタセプト
- ヒト細胞障害性Tリンパ球抗原-4. (CTLA-4)の細胞外ドメインとヒト免疫グロブリンG定常領域から構成される融合タンパク質であり、その構造からCTLA4-Igとも呼ばれる。その製剤は生物学的製剤の一つとして抗リウマチ薬などとして使用されている。
今回の論文のポイント
- 本論文の結果より、ステロイドやアバタセプト以外の免疫抑制剤(TNF-α阻害薬など)で治療を受けている自己免疫疾患の患者さんはmRNAワクチンによるCOVID-19に対する免疫反応が長期的に減弱することが推定されます。
- 実際、TNF-α阻害薬はCOVID-19に対する治療薬としてFDA(アメリカ食品医薬品局)に承認されていることから、これらの薬剤を長期にわたって服用した場合、ワクチン効果の減弱を含めた様々な副作用が起こり得る可能性を考慮する必要があります。
- 文献1
- Yamaguchi Y et al., Persistence of SARS-CoV-2 neutralizing antibodies and anti-Omicron IgG induced by BNT162b2 mRNA vaccine in patients with autoimmune inflammatory rheumatic disease: an explanatory study in Japan, The Lancet Regional Health - Western Pacific Published: December 19, 2022