医学・生命科学全般に関する最新情報


先々週、パーキンソン病に対するGLP-1受容体作動薬の臨床治験の結果を報告した論文を取り扱いましたが(エキセナチドのパーキンソン病治療効果は確認されず;第3相臨床試験〈2025/3/04掲載〉)、他方では、GLP-1受容体作動薬は、すでに、2型糖尿病患者や肥満症の治療に用いられています。しかしながら、一つの不安材料は、自殺傾向との関連性が疑われていることです。この問題を調査する観察研究がいくつか実施されているものの、結論には至っていません。これに対して、米国食品医薬品局(FDA)は、糖尿病および肥満症治療薬のGLP-1受容体作動薬と同剤服用患者の自殺念慮・自殺行動の報告について予備的評価では、因果関係が明らかな証拠は見つからなかったものの、自殺念慮・行動のリスクを最終的には除外できないとして、昨年1月11日の時点で、さらに調査を継続すると発表しました。このような状況において、カナダ・ケベック州・モントリオ−ルにありますLady Davis研究所のSamantha B. Shapiro博士やMcGill大学の共同研究者らは、英国の国家統計局死亡登録データベースを用いた大規模前向きコホート研究を行い、DPP-4阻害薬またはSGLT-2阻害薬の使用を対照薬群として比較・解析することにより、2型糖尿病患者のGLP-1受容体作動薬の使用は、自殺傾向のリスク増加とは関連していないことを示しました(図1)。その結果が最近のBMJに掲載されましたので(文献1)、今回はそれを紹介致します。GLP-1受容体作動薬は、すでに、臨床的に広く使われていることを考慮すれば、とりあえずは、一安心と言ったところでしょうか。
文献1.
Glucagon-like peptide-1 receptor agonists and risk of suicidality among patients with type 2 diabetes: active comparator, new user cohort study., Samantha B Shapiro et al. BMJ 2025; 388: e080679
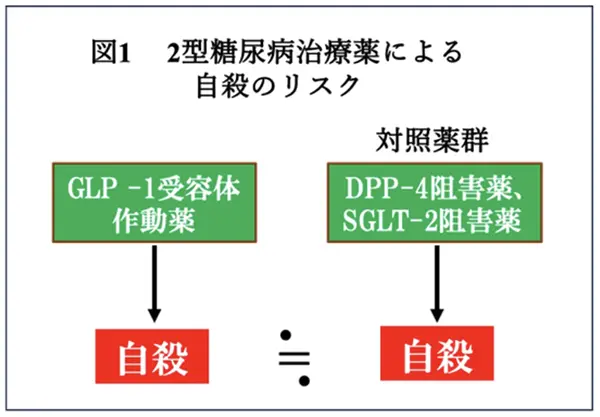
GLP-1受容体作動薬と自殺傾向との関連性が懸念されており、これを調査する観察研究がいくつか実施されているものの、結論が出るまでには至っていなかった。したがって、本プロジェクトは、GLP-1受容体作動薬の使用と自殺傾向のリスク増加との関連性をコホート研究により検討することを研究目的とした。
以上の結果より、2型糖尿病患者のGLP-1受容体作動薬の使用は、DPP-4阻害薬やSGLT-2阻害薬に較べて、自殺傾向のリスク増加とは関連していないことが推定された。