
第8回都民講座では、東京医科歯科大学教授の戸原玄(戸原 玄先生を講師にお迎えし、オーラルフレイル対策について、ご講演いただきました。
高齢化の進展に伴い、肺炎で亡くなる方が増えています。高齢者が肺炎になるきっかけとして多いのは、筋力が弱り飲み込む力が衰え、食べ物が気管に入ってしまうことです。飲み込む力が弱くなっている場合は、ひどく痩せている、目が覚めていない、声が出にくい、痰が異常に多い、口が非常に汚い、口が異常に乾燥している、呼吸が安定していない、首の部分の筋肉が硬い、ひどい猫背である、ことが多いです。一見、口腔と結びつかない点からも、その危険は潜んでおり、食事時のテーブルが高すぎないか、足底が安定しているか、椅子からずり下がっていないかなど、姿勢の大切さについて、ご講演いただきました。また、口の中を汚いままにしておいて細菌が繁殖すると、虫歯や歯周病になるだけでなく、歯肉の近くには血管が通っているため細菌が血管に入り込んで心臓に届いた結果、細菌性心内膜炎を起こすことになります。血管の場合には動脈硬化、肺の場合には誤嚥性肺炎を引き起こします。細菌を増やさないためには、歯磨き、検診、治療が必要です。まさに、「口は、生きるの一丁目一番地」であることを教えて頂きました。
さらに、特別ゲストとして、戸原先生チームの歯科往診を受けている筋萎縮性側索硬化症療養者である岡部宏生(おかべ ひろき)さんにもコメントを頂き、舌を噛まないようにするためのマウスピースの工夫など、口から食べることがなくても、口腔内環境を整えることの大切さをご紹介頂きました。
講演後のアンケートでは、「勤務先でも十分取り入れられる内容なので、他のスタッフにも情報共有が出来ればと思います。」「大変参考になりました。歯科衛生的見解にとどまらず、姿勢や筋力に着目されていたのは新鮮でした。」といった感想をいただき、ご講演後には、先生への質問の列が途切れることなく続きました。
3月20日(水)、第45回サイエンスカフェ in 上北沢「電気で動く身体を見てみよう!」を、脳機能再建プロジェクト 西村 幸男プロジェクトリーダーを話題提供者として、対面式で開催しました。
今回のサイエンスカフェでは、私たち人間の体から発生している電気がどれくらいなのか、確認してもらうとともに、私たちの体が電気で動いていることを実感してもらうために、何ボルトで身体が動くのか、調べていただくことを目的に開催しました。私たちの身近にあるもので電気を発生するものと言えば乾電池が挙げられますが、この電気の強さは1.5ボルトです。そして、乾電池の+極と-極を手で挟むと、体の中に1.5ボルトの電気が流れますが、感じることはありません。また、アマゾン川に住んでいる電気ウナギは300から800ボルト、つまり、乾電池200から533本分の電気に相当しますが、これを発生して獲物を痺れさせることで捕まえます。さらに、電気ウナギと家庭用の電源を比較すると、家庭用電源は100ボルトのため、電気ウナギの方が高くなるとお話ししました。それでは問題です。
問題1 私たち人間の体から発生している電気の強さは乾電池で何本分でしょうか?
問題2 私たち人間の体は乾電池で何本分で動くでしょうか?
という、二つの問題の答えを出すために、参加者には二つの実験を体験していただきました。一つ目の実験としては、電圧を測ることができるオシロスコープを使って、腕の筋肉は何ボルトを出しているか、計測していただきました。また、二つ目の実験としては、低周波治療器を使って腕の筋肉に電気刺激をして、何ボルトの電気が流れると筋肉が動くのかについて電圧を測っていただきました。そして、この二つの実験を通じて、一つ目の実験から、筋肉は乾電池何本分の電気を出しているか、また、二つの目の実験から、乾電池が何本あったら筋肉を動かせるか、について参加していただいたみなさんに考えていただきました。実験後、各班から回答していただき、一つ目の実験に関しては、みなさんの回答は乾電池1本分に満たない、0.01から0.02本程度というものでした。続いて、二つ目の実験に関しては、5から8本分という答えでした。これらの回答を踏まえて、身体が動く仕組みについて、脳からの発せられる電気信号が脊髄を通って筋肉にまで届き、動くこと、また、電気が多く流れると、少なく流れた場合よりも多くの筋肉が収縮して、強い力を出すことができるようになることを説明しました。

3月15日(金曜日)、当研究所は、「Social Determinants of Mental Health(メンタルヘルスの社会的決定要因)」と題して、第26回都医学研国際シンポジウムを開催しました。国際シンポジウムは、国内、国外の研究者を招聘し、医学に関連する最先端の研究成果について活発に討議することを目的としています。今回は、英国と米国から5人の研究者をお招きし、人々のメンタルヘルスに与える社会的環境要因とそれらに着目した予防戦略に関する最新の研究成果をご発表いただきました。
近年の多くの先行研究によって、統合失調症やうつ病などの精神疾患の発症には、社会的環境要因が大きく影響を与えていることが明らかとなっています。特に、人間の精神的発達に重要な意味を持つ乳幼児期から小児期、そして思春期といった人生早期のライフステージの社会的環境は、その後のメンタルヘルスや生活に長期的な影響を及ぼすことがわかっています。ロンドン大学のマーカス・リチャーズ教授は、約 5,000 人の新生児を70年以上追跡した英国出生コホート研究の成果を紹介し、小児期・思春期の教育環境や教育機会が、人間のメンタルヘルスを長期的に支え、また認知症の予防にも寄与する可能性を示されました。ハーバード大学のビクラム・パテル教授は、ご自身の研究を含め世界で行われている介入研究の最新知見を紹介し、胎生期から思春期にかけての社会的環境に働きかけることで、多くの人々のメンタルヘルスを長期的に増進しうる可能性を示されました。特に小児期の貧困や虐待などを予防する社会政策やサービス開発の重要性を指摘されました。社会健康医学研究センターからは、センターが運営している Tokyo Teen Cohort Study のデータに基づいて、いじめとその後遺症がもたらす長期的な影響と、それを予防するための学校風土(school climate)の改善プロジェクトの重要性が示されました。医学研が東京都と連携して進めている「学校の居心地向上検証プロジェクト」についても紹介しました。
世界中で行われてきた大規模疫学研究によって、幻聴や幻視といった幻覚体験は、統合失調症など精神疾患を経験している人たちのみならず、一般の多くの人々が経験していることが明らかとなっています。スタンフォード大学のターニャ・ラーマン教授は、世界の様々な地域で文化人類学的な研究を行い、その結果、国や地域の文化差によって、幻聴の内容が異なる可能性を示しました。また、王立ロンドン大学のステファニ・ハッチ教授やニューヨーク市立大学のディドリ・アングリン准教授らは、社会システムの中でマイノリティの立場に置かれている人々のメンタルヘルスが脅かされていること、多様性を尊重する社会システムに転換することの重要性を示されました。
精神疾患やメンタルヘルス問題は、社会環境の影響を受け発生していること、ゆえに、生物学的研究だけでなく、社会医学研究を推進し、エビデンスに基づいて社会システムに働きかける方策を見出していくことの重要性をあらためて認識する機会となりました。


1月20日(土曜日)、「がん遺伝子パネル検査の最新の動向」と題して、2023年度第7回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、都立駒込病院 医長の池上 政周先生を講師にお迎えしました。
まず、当研究所がん免疫プロジェクトの丹野秀崇プロジェクトリーダーから、「遺伝子を活用したがん治療法の進展」と題してお話ししました。私たちは体内の多様なタンパク質により生命機能を維持しています。そのタンパク質の設計図が遺伝子ですが、様々な要因から傷付くことで、タンパク質が壊れたり、異常な振る舞いをするタンパク質が生み出されることがあります。タンパク質の機能異常は、細胞の過剰な増殖、つまり、がん化を引き起こしかねません。私たちの体は、がん化を防ぐために多様な免疫細胞を血液中に持っています。その中でも、T細胞は特に重要な役割を担っています。正常な細胞が何らかのダメージを受けて遺伝子に異常が生じると、これらの細胞はT細胞に対して、自らを排除するよう指示します。T細胞はTCR(T細胞受容体)という特殊なセンサーを使って、がん細胞や感染した細胞によって生産される異常なタンパク質を識別します。そして、これら異常な細胞を効果的に排除し、体を守ります。最近、このTCRを用いた遺伝子治療の臨床試験が進行しており、これは、がん患者さんのT細胞を取り出して、がんを認識するTCRを導入し、この遺伝子導入T細胞を増殖後、患者さんに戻すものです。これにより、効果的に体内でがん細胞を死滅させることができるとお話ししました。
続いて池上先生から、「がん遺伝子パネル検査の最新の動向」と題してお話しいただきました。がん遺伝子パネル検査は主に治療薬を使用できる遺伝子異常がないかを検索する目的で行われます。ヒトには約23,000個の遺伝子があり、このうち、約3%の700個が発がんに関連しています。次世代シーケンサーと呼ばれる一度に大量の遺伝子を調べる機器が登場したことで、遺伝子変異の検出が容易になり、がん遺伝子パネル検査が一般的になりました。検査した結果、遺伝子に変異が見つかれば、その変異に対する効果が期待できる治療薬を選び使用することになります。しかし、現時点ではまだまだパネル検査には課題が多いそうです。現行の制度では、パネル検査を受けることができるのは、がんに対する標準治療が終了し、今後の治療の選択を見極める必要が生じた患者さんになります。ただ、進行の早いがんですと標準治療中に亡くなってしまったり、標準治療終了後に新規治療を受けるのは気力・体力的にも厳しく、新規治療に結び付かないことが多いそうです。従って、標準治療前にパネル検査を実施して、治療の選択肢を広げることの重要性を強調されていました。また、パネル検査を実施して遺伝子に変異が見つかったとしても、それに対応できる治療薬が存在しなかったり、その変異ががんの悪性度にどのように寄与しているのかが現時点では分からないことも多いそうです。池上先生らのグループを初め、遺伝子変異に対応できる治療薬の探索や遺伝子変異の意義を解明する取り組みが数多くされていることをご紹介いただきました。
講演後のアンケートでは、「医学の進歩に希望を持ちました。今後も、こうした最新の情報を一般の者もわかるような形で教えていただけるとありがたく思います。」「私自身昨年泌尿器科で細胞を取る検査手術を受け、2ヶ所良性腫瘍が確認され、引き続き血液検査などで経過観察を行っています。本日の内容はたいへん参考になりました。」といった御意見を多く頂きました。
笠原 浩二(学術支援室)
第44回 サイエンスカフェ in 上北沢を、話題提供者の幹細胞プロジェクト所属東京都立大学の大学院生の長谷部愛佳さん、江川優花さん、船田淳太さん、およびリサーチアシスタントを務めた6名の大学院生とともに当研究所の講堂にて対面式で開催しました。「蛍光ペンは、なぜ明るく見えるのか?」を例に蛍光とは何かについてお話しし、水中に生息するワカメなど藻類の仲間であるスピルリナが、フィコシアニンとクロロフィルと呼ばれる二種類の蛍光色素を持っていることを紹介しました。その後の実習で、スピルリナから青色のフィコシアニンを水で抽出し、また緑色のクロロフィルをエタノールで抽出しました。それを紫外線で照らすと、それぞれピンク色と赤色の蛍光で光ることを紫外線防護メガネをかけて観察しました。そしてブロッコリー、ピーマンやサニーレタスなどの野菜に紫外線を当ててもクロロフィルの蛍光によって赤く光ること確認しました。また身近なものとしてビタミンB2、部屋干し用液体洗剤、使用済ハガキ、蛍光灯、蛍光インクが蛍光で明るく光ることを観察した時は、参加してくださった30名の小学生の皆さんから歓声が上がっていました。最後に再生医療プロジェクト所属東京医科歯科大学の大学院生の安田有冴さんが、フィコシアニンとクロロフィルが太陽光からエネルギーを吸収し、そのエネルギーで光合成が可能となり水と二酸化炭素から糖と酸素が作られること、部屋干し用洗剤が蛍光増白剤によって衣類の黄ばみを抑えるしくみ、ハガキが蛍光インクのバーコードによって住所の仕分けが自動化されていることを解説しました。当日は開催時間前と休憩&ティータイムに正井所長によるピアノの生演奏もあり、終了後には「白衣着用により科学者の姿を体験できるコーナー」を設け、始終和やかな雰囲気の中で進められました。「実験がとっても楽しかったです。先生、一人ひとりの説明がとても分かりやすかったです。また来たいです。」「子どもが飽きないように休憩やおやつをご用意して下さり、飽きずに参加できました。リサーチアシスタントのみなさんが優しく接してくださったので楽しく、取り組めました。ピアノ生演奏に癒されました。ありがとうございました。」「保護者、幼児も一緒に参加させていただけたのでとても楽しめました。」などの感想をいただきました。


11月17日(金曜日)、「人生100年時代の認知症予防のために」と題して、2023年度第6回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、九段坂病院 院長の山田 正仁先生を講師にお迎えしました。
社会の超高齢化に伴い、認知症の人やその前段階である軽度認知障害の人は急増しています。認知機能は急激に衰えることはなく、徐々に、物忘れが目立ち始めるものの日常生活を送る上では支障がない軽度認知障害と呼ばれる状態から、さらに悪化すると、出来事自体を忘れてしまい、日常生活に支障が生じるようになってしまう認知症へとつながっていきます。認知症として、アルツハイマー病、レビー小体型認知症、脳血管性認知症が知られています。このうち、レビー小体型認知症は、記憶や判断の障害等の認知機能障害が見られ、また、認知機能が日によって変動し、他にも、運動が障害され動きがゆっくりになるパーキンソン症状や幻視等が見られます。血管性認知症は、脳梗塞や脳出血等の脳の血管の病気により神経細胞が障害されると起こるもので、脳の病気が再発するたびに認知症が悪化していきます。アルツハイマー病は、記憶を司る脳の海馬が委縮し、その機能が衰えることが特徴です。症状の進行は、日付が思い出せないこと等から日常生活に支障を来たすことから始まり、そのうち、場所もわからなくなり、徘徊等の問題行動が現れて介護が必要になり、重度になると、人物もわからなくなり、施設への入所が必要になったり、あるいは、寝たきりの状態になってしまいます。また、アルツハイマー病へのかかりやすさの要因として、遺伝的要因、加齢の他に、高血圧・糖尿病等の生活習慣病や、これにつながる生活習慣、うつ病、頭部外傷が挙げられます。一方、かかりにくくさせる要因には、運動、知的活動・社会的活動、教育や、食事習慣として野菜・果物・魚・カロリー控えめの食事が挙げられるとお話しいただきました。
講演後のアンケートでは、「医療者や地域のサービス提供者だけでは、関わっている方を何とかするのに精いっぱいで、もっと理解が深まり認知症の方も地域で暮らしやすい環境になるといいと思っています。そのためにこのような講座を開いていただくことはとても意味のあることだと思います。これからも認知症のことを取り上げていただければと思います。」「都民講座と聞いて一般的な簡単なものかと思いきや専門的かつわかりやすく、しかも先端を行くような内容で非常に興味深く面白かった。認知症に興味が無かったが初めて面白いと思った。」といった御意見を多く頂きました。

10月10日(火曜日)、「『聴こえ』と健康な未来社会」と題して、2023年度第5回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、大阪大学大学院医学系研究科教授の日比野浩先生を講師にお迎えしました。
健康な聴覚は人間の生活に欠かせない感覚ですが、難聴の患者数は国内に1,000万人と、その数は糖尿病に匹敵するといわれています。また、難聴は、コミュニケーションや生活の質を低下させ、中年期の難聴は認知症の最大リスクといわれ、さらに、うつ病や社会的孤立の要因ともいわれています。子どもにとっても難聴は大きな問題となり、言語の獲得、会話や脳の発達に大きな影響を与えます。難聴には、先天性難聴の約7割を占める遺伝性難聴、加齢性難聴、ある種の薬剤の服用に伴う薬剤性難聴、突発性難聴、めまいを伴う難聴であるメニエール病、騒音にさらされることで起こる騒音性難聴がありますが、先天性の遺伝性難聴を除き、明確な原因は明らかになっていません。難聴に対する医療面での対応として、高度の難聴の場合には人工内耳を、中程度の場合には補聴器を使うことが多いですが、補聴器の使用に関しては、個人ごとに調整するのに専門的知識が必要であり、細かい操作が高齢者には難しいことから、使用をやめてしまう方もいるようです。臨床では難聴に関し、この25年間にわたり診断技術が飛躍的に進歩し、難聴の早期発見のための遺伝子検査が確立されました。今後、さらに病態の診断技術が進み、難聴の種類を細分類できるようになれば、創薬や次世代型の人工聴覚器に役立つものとなり、さらに、デジタル技術の応用により、生活の中で聴こえを自動的にチェックし守るようなスマート難聴予防システムといったものの開発も進むのではないかと、お話しいただきました。
講演後のアンケートでは、「いつも興味深いテーマでの開催、有難うございます。特に高齢者向けの内容は、日頃の生活にも役立たせて頂いております。」「現在難聴者にスマホによるコミュニケーション力向上を支援しています。専門的で、とても面白い内容でした。」「補聴器の他に「人工内耳」があることを初めて知りました。聴こえの仕組みは有意義で参考になりました。」といった御意見を多く頂きました。
10月28日(土曜日)、「From bench-to-bed sideの新たな展開~ALS診療ガイドライン2023を踏まえて~」と題して、第13回都医学研シンポジウムを開催しました。今回は、ALSに関する基礎研究の最新情報及びALSの臨床研究と新たな介入・治療法をご紹介しました。ALSは、全身の筋萎縮と筋力低下を特徴とする進行性の神経変性疾患で、孤発性患者の殆どの脳・脊髄病巣に核タンパク質の一種であるTDP-43が蓄積しています。長年、ALSは、治療法のない疾患とされてきましたが、分子生物学やゲノム研究等の進展、治療介入技術の進歩により治療開発が進み、現在、神経変性疾患の中で研究が盛んな疾患の一つとなっています。
前半の基礎研究の最新情報では、まず、当研究所の長谷川 成人プロジェクトリーダーから、2006年と2008年に、ALSや前頭側頭葉変性症(FTLD)の患者脳等にTDP-43の異常病変が蓄積していることを明らかにし、最近では、ALSやFTLDの患者脳に蓄積するTDP-43の構造解析を行った結果、それぞれの疾患で折りたたみ構造が異なっており、この違いにより異なる病態の疾患が発症することが示唆されるとお話ししました。次に、東北大学の青木正志先生から、ALSの原因遺伝子のTDP-43あるいはFUSの変異に伴う患者からのiPS細胞を使った解析や、患者iPS由来の細胞モデルによる治療薬の研究についてお話しいただきました。続いて、滋賀医科大学の漆谷 真先生から、TDP-43を凝集する病的モデルとTDP-43を特異的に認識する抗体を作製し、これらを用いてモデルマウスを作製し解析した結果、その症状は運動麻痺よりも精神症状が主となることを観察したとお話しいただきました。最後に、愛知医科大学の熱田直樹先生から、同大学が事務局を担っているJaCALS(Japanese Consortiumfor ALS Research)は、ALS患者の臨床・遺伝情報の解析を通じて病態解明と治療法の開発を目指す組織で、ALSの原因遺伝子は複数あり、それぞれの遺伝子変異を有する患者の頻度は国や民族ごとに異なるため、原因を明らかにするため解析を行っているとお話しいただきました。
後半のALSの臨床研究と新たな介入・治療法では、まず、徳島大学の和泉 唯信先生から、現在、リルゾールとエダラボンの2剤だけ保険承認されているなかで、治療薬を増やすため、高用量メチルコバラミンの有効性と安全性を検証しているとお話しいただきました。次に、東邦大学の狩野修先生から、1970年代に米国で始まった多職種の専門家の診療を受けられるALSクリニックという専門外来を同大学では2017年に開設し、リハビリテーション療法士、呼吸ケア看護師、栄養士等、多職種の専門家が同時に対応したり、カンファレンスで患者の課題を多職種で解決を目指すことで、予定外入院の減少効果があったことを報告いただきました。続いて、都立神経病院の清水俊夫先生から、ALSでは初期から体重減少がありますが、骨格筋量の減少や嚥下障害による食事量の低下は生命予後と関連しています。診断後のBMIの増加は生命予後の改善と関連するという報告もあり、診断時からの栄養介入の重要性が示唆されているとお話しいただきました。最後に、当研究所の中山優季ユニットリーダーから、ALSは、事例ごとのフィールドワークやその蓄積により、ケアを築き上げてきたこと、そして、気管切開式人工呼吸(TIV)者の追跡調査から、TIV導入までの体重減少が大きいほどその後の進行も早いことがわかり、これらの知見はALS診療ガイドライン2023において引用されることになったことを報告しました。

去る 2023年 10月 16日、国際シンポジウムが開催されました。本シンポジウムは、先だって行われた島根県松江市で開かれたコールドスプリングハーバーアジア主催の「Yeast and Life Sciences」ミーティングに来日した著名な研究者を招待する形で行われました。国際シンポジウムでは、酵母研究からヒト、個体研究とまるで進化の系譜を辿るかのような非常に興味深い研究成果の発表が続きました。
Remus 教授(Sloan Kettering 研究所)は、DNA 複製フォークがその進行の障害となる DNA 構造をどのように認識して乗り越えるかを生化学的に解析した結果を発表しました。Qing Li 教授(北京大学)は、細胞増殖に伴って合成される DNA 分子に巻き付いているヒストン分子の分配に関わる研究を報告しました。Remus 教授と Li 教授は、PI になってまだ 10 年ほどの新進気鋭の研究者であり、すでに教科書に記載される可能性のある発見を発表しており、このシンポジウムを通して議論できたことは大変な収穫でした。また Foiani 教授(イタリア iFOM 研究所前所長)の発表は印象的でした。Foiani 教授は、細胞の物理的なストレスの応答に関する研究でした。癌細胞は、密に存在する正常細胞を押し除けながら(物理的ストレスを受けながら)、固形腫瘍を形成しています。Foiani 教授の発表では、物理的なストレスを感じながら増殖する細胞には、 DNA 損傷が発生していること、また、がん形質をより獲得しやすいことを示していました。
シンポジウム中に活発な議論が展開されている様子を見ると、コロナ禍で断絶されていた対面での研究者間の交流活動が再開されたことを実感できました。特に医学研外の研究者の参加も多く、異なる分野の方々との交流ができたことは、新たな発見や刺激を受けることができ、非常に有意義な時間でした。シンポジウム終了後に開催された懇親会では、招待講演者だけでなく学生さんも加わり、ざっくばらんな雰囲気で交流を深めることができました。
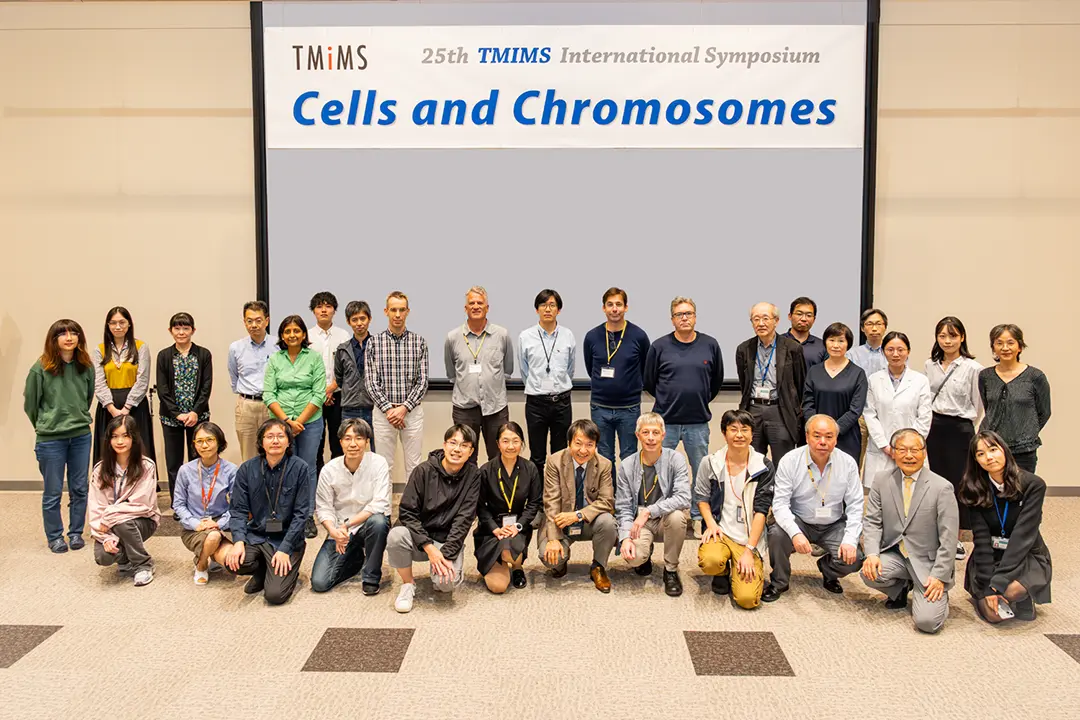

9月19日(火曜日)、「現代のアディクション」と題して、2023年度第4回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、神戸大学大学院医学研究科デジタル精神医学部門特命教授の曽良一郎先生を講師にお迎えしました。
まず、当研究所依存性物質プロジェクトの井手聡一郎副参事研究員から、「身近で多様なアディクション」と題してお話ししました。アディクションは、大麻等の薬物やアルコール、タバコ等を対象とした依存である物質依存に加え、ギャンブルやゲーム、盗癖等の特定の行動を繰り返し行ってしまう行動嗜癖も含めた概念です。近年、アディクションの問題は多様化と拡大が進んでおり、国内外における問題をお伝えすると共に、アディクション問題解決に向けた、基礎研究の取り組み状況をお話ししました。

続いて曽良先生から、「ネット・ゲーム依存の基礎知識と対応について」と題してお話しいただきました。オンラインゲーム等の普及に伴い、ネット・ゲーム依存は世界的に問題となっています。児童青年期では、学校が面白くない等の理由からネット・ゲームの過剰な使用が始まり、引きこもりや不登校によって依存がさらに進んでしまう悪循環が生じています。ネット・ゲーム依存は、インターネット普及前と比べ、ゲームの使用のコントロールが難しくなっていることが影響を与えています。これには、様々な原因が考えられます。オンラインではないゲームは最後までクリアすると自然にやめましたが、現在のゲームはコンテンツが頻繁にアップデートされるため、飽きることがありません。また、かつてはゲームを一緒にやろうとすると友達と集まらなくてはなりませんでしたが、現在はSNSでゲームをしようと呼びかけると簡単に仲間が集まるため、すぐに始めることができます。さらに、現実生活では対人関係が不得手でも、顔の見えないオンラインでは外交的で社交的な感覚を持ちやすいこと、加えて、現実生活での不安やストレスの軽減手段や逃避場所としてゲームが使われていることが挙げられるとお話しいただきました。一方で、ゲームを有効利用した注意欠陥・多動性障害(ADHD)のデジタル治療(デジタルセラピューティクス:DTx)に関してもお話しいただきました。
講演後のアンケートでは、「医療従事者でもありますが、子供がゲーム依存傾向あり、とてもためになる内容でした。」「私は学校薬剤師で、薬物依存等について、興味があります。とても有意義な内容で、大変勉強になりました。学校での「おくすり教室」「薬物乱用防止教室」などの保健指導にも役立ちます!」といった御意見を多く頂きました。
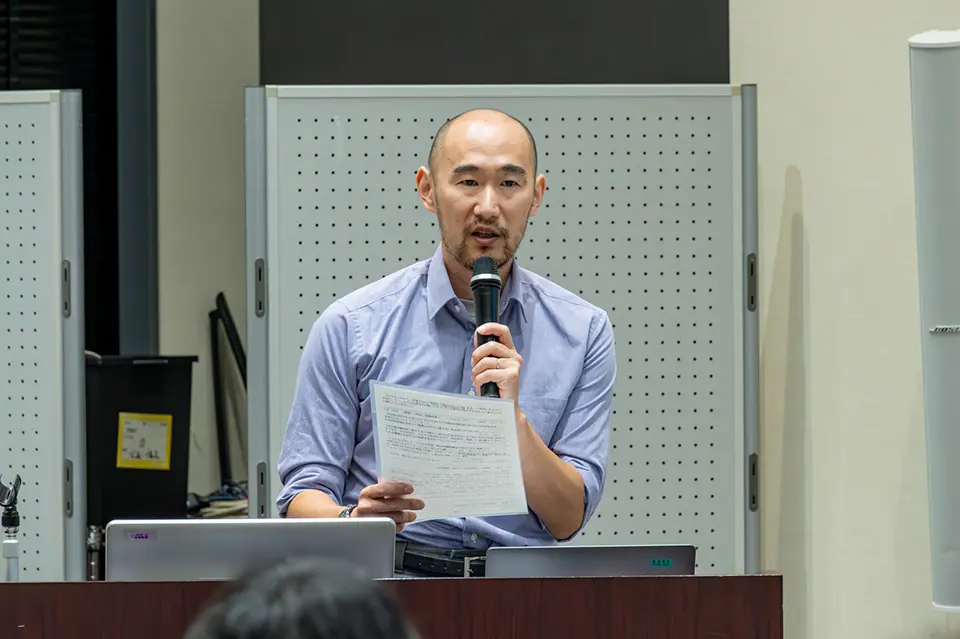
7月24日(月曜日)、当研究所では、「今語られるiPS細胞誕生への道のり」と題して、2023年度第3回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、京都大学iPS細胞研究所准教授の高橋和利先生を講師にお迎えしました。
まず、当研究所再生医療プロジェクトの宮岡佑一郎プロジェクトリーダーから、「iPS細胞誕生の衝撃」と題してお話ししました。iPS細胞が発表された2006年当時、大学院生だった先生は、初めて聞いた時に嘘だと思ったくらいの衝撃を受けました。特定の種類になった細胞は、二度と発生初期の何の細胞にもなれる状態には戻らないという考えが常識だったからです。また、先生も同じ実験材料や手法を使っていたものの、iPS細胞を作ろうという考えには全く思いも寄らなかったことから、素晴らしい研究は素晴らしいアイデアから生まれることを実感し、それを先生は今でも胸に刻んで研究を進めている、というお話をしました。
続いて、高橋先生から、「iPS細胞」と題してお話しいただきました。受精卵は全ての遺伝子を持ち、細胞分裂で数を増やしながら、皮膚や筋肉等の様々な種類の細胞になっていきます。1890年代から続いていた考え方では、皮膚の細胞であれば、皮膚であることに必要な遺伝子以外は捨ててしまうため、他の遺伝子が必要な他の種類の細胞になることはできません。ところが、1960年代に、オタマジャクシの腸の細胞の核をカエルの卵に移植したところ、予想に反し、クローンカエルが誕生しました。これは初のクローン動物であり、カエルの腸の細胞は、カエルの身体を作る全ての細胞の遺伝情報を持つことを示しています。その後、1980年代に、皮膚の細胞に筋肉の細胞で機能しているある遺伝子を入れて働かせると皮膚の細胞から筋肉の細胞になることが明らかになりました。この研究から、筋肉には筋肉の司令塔の役割を果たす遺伝子がいて、他の様々の遺伝子に働くか働かないか指示を出していることがわかりました。そして、これらの研究から、例えば、皮膚の細胞に受精卵に含まれる細胞の司令塔となる遺伝子を入れることで、発生初期の何にでもなれる細胞になることが想定されました。実際に先生が、山中先生の研究室で、マウスを使い、発生初期の細胞の司令塔と考えた24個の遺伝子を皮膚の細胞に入れたところ、期待通りあらゆる細胞に分化できる細胞を作れることを発見し、最終的に遺伝子を4個に絞り込み、2006年にiPS細胞として発表したとお話しいただきました。
「大変興味深い内容でよかった。実際に研究に携わった先生だからこそお話しできるエピソードが満載で、実際の講演時間よりも短く感じた。」といった御意見を多く頂きました。

高橋和利先生

会場の様子
笠原 浩二(学術支援室)
第43回サイエンスカフェin上北沢「身の回りのものを使って、虹色を作ろう!―酸性?アルカリ性?―」を幹細胞プロジェクトの江川優花さん、長谷部愛佳さん、船田淳太さんと一緒に事務局普及広報係の協力のもとで行いました。夏休み中の猛暑日が続くなか3年振りに対面式で行われ、当研究所 講堂に多くの小学生の皆さんと保護者様方が来てくださいました。「水溶液、pHとは何か?」についてイントロダクションを行い、身近にあるものを使った7種類の無色透明の水溶液のpHの違いをpH試験紙を使って調べました。休憩とティータイムの後、小学生の皆さんに紫キャベツを細かくハサミで切ってもらい、水を加え電子レンジで加熱することで天然色素であるアントシアニンを抽出しました。そして、大学院生スタッフの指導のもとで抽出液を一人一人スポイトで水溶液に加えてもらい、pHにより違った色に変わることを観察しました。色が鮮やかに変わったときには、皆さん目を輝かせていました。まとめとして、サンプル成分の解説、アントシアニンが含まれる果物や野菜とその意義、身体の中におけるpHの重要性についてお話し、最後にご自宅での自由研究として紫キャベツ実験をする際の方法と注意点について解説し、用意したpH試験紙と紫キャベツ抽出液を皆さんに持って帰っていただきました。「楽しかったので、また参加したい。」「勉強になって面白かった。」などの感想をいただきました。


6月9日(金曜日)、当研究所では、「基礎医学からみたパーキンソン病」と題して、第2回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、生理学研究所名誉教授の南部篤先生を講師にお迎えしました。
パーキンソン病は、手足の振るえ、動かしにくさ、強張り等の運動症状に加え、睡眠障害や便秘等を示す神経難病です。そして、日本における患者数は、60歳以上になると、100人に1人といわれ、発症する人が多いことから、大きな問題となっています。パーキンソン病の発症原因は、脳内で神経伝達物質として働くドーパミンという物質が減少することです。先生は、ドーパミンが減少した結果、脳にどのような変調を来し、どのようなメカニズムで症状が出るのかについて、実験・研究をしてきたそうです。その結果、これらの変調を修正すると症状が軽減することもわかってきたとのことでした。また、パーキンソン病の発症初期の治療は、薬物療法が中心となり、70歳から75歳まではL-ドーパ、70歳以下はドーパミンアゴニストが用いられます。ただし、薬物療法には副作用もあり、身体が勝手に動いてしまう不随意運動が現れることがあります。さらに、進行期になると、脳内の異常が発生している箇所に対し、電極を入れて電気を流して壊す脳深部刺激療法と呼ばれる脳外科的治療法が行われることがあるとお話しいただきました。

講演後のアンケートでは、「父がパーキンソン病なので受講しました。メカニズムや治療の現状がわかりやすかったです。研究によって、より安全で効果的な治療法ができると嬉しいです。」「パーキンソン病の仕組みや治療について教えていただき、病態がイメージしやすくなりました。」といった御意見を多く頂きました。
4月27日(木曜日)、当研究所では、「遺伝性神経疾患におけるカルパイン制御について」と題して、第1回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、福井大学学術研究院医学系部門教授の山田雅己先生を講師にお迎えしました。
まず、当研究所カルパインプロジェクトの小野弥子プロジェクトリーダーから、「カルパインの働きと疾患」と題してお話ししました。カルパインは、細胞内に存在するタンパク質について、その形を整えるかのように切り分け、タンパク質がきちんと機能するように助けるもので、いわばタンパク質の働きを調節しているものであるといえます。このカルパインの働きを上手く制御できないと、その結果として症状が悪化するとされている神経変性疾患は数多くあり、具体的には、アルツハイマー病、パーキンソン病やてんかん等が挙げられます。そして、カルパインの働きを制御することで、これらの疾患の病態を改善することを目的に、世界中でカルパイン阻害剤の開発が進められているとお話ししました。
続いて、山田先生から、「『脳のシワ』が無い病気、滑脳症とは?」と題してお話しいただきました。滑脳症は、一般的に脳のシワと呼ばれる脳回や脳溝がないことが特徴で、臨床症状としては、精神遅滞やけいれん等の重い症状がみられ、現状では根本的な治療方法はありません。この滑脳症の発症は神経細胞の移動障害に起因するといわれ、複数の原因遺伝子が報告されています。その中で、Lis1の遺伝子変異は滑脳症全体の6割を占め、Lis1タンパク質の減少を引き起こします。先生は、Lis1タンパク質の減少により移動障害が発生するには、何らかのタンパク質分解酵素が原因なのではないかと考えて研究を進め、それがカルパインであることを明らかにしました。そのため、先生は、カルパインの働きを妨げる阻害薬に注目されており、実験ではそのような薬剤を用いることで、運動能力や記憶・学習効果の回復・改善が見られたということをお話しいただきました。
講演後のアンケートでは、「滑脳症の子供がいるため興味があり参加しました。有効な治療法が早く見つかると良いなと思います。」といった御意見を多く頂きました。

小野弥子プロジェクトリーダー

山田雅己先生