 2021年度 開催報告
2021年度 開催報告2022/3/26 開催

オンライン開催
第39回 サイエンスカフェin上北沢
3月26日(土曜日)、当研究所では、第39回サイエンスカフェin上北沢「体内におけるがんと免疫の攻防」を、がん免疫プロジェクトの丹野 秀崇プロジェクトリーダーを話題提供者として、オンライン方式で開催しました。
がんは日本人の二人に一人が罹患するほど身近な病気ですが、その発症の仕組みは、体の設計図である遺伝子が傷付くことによるものです。がんの発生に関わる遺伝子として、原がん遺伝子とがん抑制遺伝子があります。原がん遺伝子に異常が発生すると、常に活性化した状態となってしまうことで過剰な細胞増殖を引き起こしてがんが発生し、一方、がん抑制遺伝子が壊れると、異常な細胞の増殖に対して抑制が効かなくなり、過剰なまでに増えてしまいがん化する、とのことでした。また、わたし達の体にはがんを排除する免疫システムが備わっており、日々体内からがん細胞を排除しています。この仕組みは、免疫の役割を担っているT細胞がT細胞受容体(TCR)を使って、がん細胞の表面に出ている異常なタンパク質を認識し、がん細胞を破壊するものである、とお話ししました。さらに、体内にはTCRが1億種類以上も存在し、それぞれ認識する異常タンパク質が異なるとのことでした。最後に、最近、世界中で研究が盛んになっているTCRを用いた遺伝子治療をご紹介しました。これは、がん患者から取り出したT細胞にがんを認識するTCRを遺伝子導入することで、T細胞ががん細胞を認識できるようにし、そのT細胞を増殖後、がん患者に戻すというものです。この治療法は効果が高いものの、一般的にはなっていません。この理由として、現在の技術では、各細胞が異なるTCR配列を発現しているため、1細胞ずつ単離して配列を決定する必要がありますが、これでは数百種類の細胞しか解析できず、がんを認識するTCRの発見が困難なためです。そこで、丹野リーダーの研究室では、一つの細胞を高速に解析できる装置を開発し、数万種類のTCR配列を1細胞レベルで同定することを可能にした、とお話ししました。
アンケートでは、「遺伝子によるタンパク質生成のプロセスや免疫の働きなど、とてもよく理解することができました。基本的な内容から教えて頂き、大変分かりやすかったです。」といった御意見が数多く寄せられました。

がん免疫プロジェクトの丹野 秀崇プロジェクトリーダー
 お茶大-都医学研 連・協~協定締結記念- 3月2日開催 - キックオフシンポジウム
お茶大-都医学研 連・協~協定締結記念- 3月2日開催 - キックオフシンポジウム
3月2日(水曜日)、当研究所では、お茶の水女子大学(以下、「お茶の水大」) - 東京都医学総合研究所 連携・協力に関する協定締結記念キックオフシンポジウムをオンライン方式で開催しました。お茶の水女子大学と東京都医学総合研究所は、相互の人材や研究基盤を活かして総合力を発揮し、広く科学技術の発展に寄与するため、昨年、連携・協力に関する協定を締結したところです。今回、協定の締結を記念し、両機関がお互いに相互理解を深め、今後の相互の教育研究活動の発展を目指したいと考え、キックオフシンポジウムを企画しました。

難病ケア看護ユニットの中山優季ユニットリーダー
開会挨拶の後、当研究所田中理事長及びお茶の水大の佐々木泰子学長からのご挨拶、来賓挨拶として、事業推進担当の渋谷恵美部長及び文部科学省産業連携・地域振興課の井上睦子課長よりご挨拶いただきました。続いて、当研究所正井所長及びお茶の水大の太田裕治副学長から各機関の紹介を行いました。その後、両機関の研究について講演を行いました。まず、お茶の水大から、基幹研究院自然科学系の佐藤敦子准教授より、「未来発生進化学:環境は生物の未来をどう変えるのか?」、続いて、同じく基幹研究院自然科学系の飯田薫子教授より、「ミトコンドリア機能低下と疾患;栄養代謝の視点から」と題してお話しいただきました。さらに、当研究所から、難病ケア看護ユニットの中山優季ユニットリーダーより、「筋萎縮性側索硬化症(ALS)における意思伝達維持を目指した集学的研究」、脳神経回路形成プロジェクトの丸山千秋プロジェクトリーダーより、「脳発生学研究にたどり着くまで」と題し講演しました。
その後、当研究所で研究しているお茶の水大の学生が、当研究所で研究を行うことになった経緯や研究生活、研究内容等を紹介しました。まず、人間文化創成科学研究科修士課程2年のNgo Thi ToTrinhさんは、2018年にベトナムのホーチミン市で開かれた会議で、正井所長と話したことをきっかけに来日し、大学院で学びながら、ゲノム動態プロジェクトで研究していることを話しました。続いて、理学部生物学科4年の高瀬未菜さんが、1年の時から、研究分野は決まっていなかったものの実験をしたいという希望を持ち、大学の先輩から当研究所で実験ができることを教えてもらったことから、認知症プロジェクトで研究をすることになったこと、その後、同プロジェクトで実験を重ねるうちに脳に興味を持ち、現在、大学では脳関連の研究室に所属していること、今後は研究室と同プロジェクトとの共同研究の懸け橋となりたいという話がありました。
今回のキックオフシンポジウムを契機として、今後、両機関がさらに人や物そして知識の交流・協力を深め、双方における教育研究活動を相乗的に推進していくことが期待されます。
 第8回都医学研都民講座 - 2月25日開催 - 認知症とともに生きる人の
第8回都医学研都民講座 - 2月25日開催 - 認知症とともに生きる人の2月25日(金曜日)、当研究所では、「認知症とともに生きる人の希望を支えるケア:心理社会的アプローチと家族支援」と題して、第8回都医学研都民講座をオンライン方式で開催しました。今回は、東北大学医学部・医学系研究科精神看護学分野准教授の中西三春先生を講師にお迎えしました。

中西三春先生(東北大学医学部・医学系研究科精神看護学分野准教授)
認知症は根治的な治療がなく、10年単位の経過を辿るケースが多く、徐々に能力や機能が失われていきます。このため、症状が進行するにつれ、ケアの目標が変わっていくそうです。つまり、症状が軽度のときには生命の延長を目指し、症状が重くなるにつれ、機能の維持やQOLの最大化を重視していくようになるということです。また、幻覚、妄想や介護抵抗等の心理的反応や行動は、行動・心理症状と呼ばれますが、これは認知機能の障害とイコールではなく、あくまで、認知機能障害による生活障害と環境との相互作用で起こるとのことでした。このため、行動・心理症状はニーズの現れと考え、目に見える行動を抑えようとするのではなく、目に見えない本人のニーズを満たすようにケアをしていく方向に変わってきているそうです。さらに、中西先生は昨年度まで当研究所に在籍していた際、都との間で行っていた行動・心理症状に対応したケアプログラムの開発に携わっていましたが、これは、在宅を中心としたケアにおいて、どの職種も標準的な認知症ケアが提供できるようにすることを目的としたものです。

西田淳志(社会健康医学研究センター長)
このケアプログラムは、4つのプロセスに分かれ、チーム内で話し合いながら、まず行動・心理症状を共通の尺度で得点化することから始め、その行動・心理症状の背景にどのようなニーズが潜んでいるのかを分析し仮説を立て、そのニーズを満たすためのケアを計画し、実行します。このケアを行った結果について再度得点化し、前回と比べ改善したかを評価します。評価の結果、改善があまり見られない場合には、行動・心理症状の背景を再度分析し、仮説を立て、ケアを計画し、実行するというサイクルを改善するまで続けていくことになります。このケアプログラムでは、チーム内で視点と対応を揃え、見える化で仮説と検証を繰り返していくことが重要であると、お話しいただきました。
講演後のアンケートでは、「認知症が10人に1人となるというのは衝撃でした。しかし、この講座を聞いて今後訪れるかもしれない介護側、介護される側の立場を想像して、恐れる気持ちが少し和らいだように感じています。」といった御意見を多く頂きました。
 第7回都医学研都民講座 - 1月21日開催 - スギ花粉症の治療と
第7回都医学研都民講座 - 1月21日開催 - スギ花粉症の治療と2022/1/21 開催

第7回都医学研都民講座 オンライン開催
1月21日(金曜日)、当研究所では、「スギ花粉症の治療と研究の最近の動向」と題して、第7回都医学研都民講座をオンライン方式で開催しました。今回は、日本医科大学耳鼻咽喉科准教授の後藤穣先生を講師にお迎えしました。
まず、当研究所花粉症研究室の佐伯真弓主席研究員から、「舌下免疫療法が効くしくみを探る」と題してお話ししました。舌下免疫療法は、原因となる抗原を繰り返し投与することで、その抗原に対する感受性を低下させる療法です。この舌下免疫療法は、スギ花粉症の根治療法として有用ですが、治療期間が3年以上も必要となる上に、30%程度の患者さんでは効果がみられない問題点もあるそうです。これを改善するには、事前に治療の効き具合等が予測できるようにすることが必要です。現在でも、舌下免疫療法が効くメカニズムは明らかになっていないため、治療の効果のあった患者さんとなかった患者さんの血液サンプルを用いて、どのような因子が作用しているのか分析しているとお話ししました。
続いて、後藤先生から、「舌下免疫療法による根治を目指した治療」と題してお話しいただきました。花粉症等のアレルギー性鼻炎の治療には、大きく分けて、抗原除去・回避、薬物療法、アレルゲン免疫療法及び手術の4種類があります。このうち、アレルゲン免疫療法に含まれる舌下免疫療法は、疼痛がなく、自宅で投与でき、副反応の多くが局所反応のみ、といった多くの長所があることから、日本でも普及してきているとのことでした。また、現在では、舌下免疫療法の適用範囲が当初の成人だけでなく、小児にも拡大されたそうです。なお、臨床試験では、3年間にわたる治療を終え、服薬をやめた後でも症状の改善が続いたことから、舌下免疫療法は根治療法になる可能性があることをお話しいただきました。
講演後のアンケートでは、「今回の内容を家族と共有し、舌下免疫療法を受けてみたいと強く思いました。」といった御意見を多く頂きました。

後藤 穣 先生
 第38回サイエンスカフェ - 12月18日開催 -
第38回サイエンスカフェ - 12月18日開催 -2021/12/18 開催

第38回サイエンスカフェin上北沢 オンライン開催
12月18日(土曜日)、当研究所では、第38回サイエンスカフェin上北沢「体内時計って何? 24時間リズムの不思議。」を、体内時計プロジェクトの吉種 光プロジェクトリーダーを話題提供者として、オンライン方式で開催しました。
体内時計という言葉は、睡眠のように毎日繰り返されるリズムとして、昨今良く使われますが、学術的には、このリズムを概日リズムと呼び、これを生み出す仕組みを概日時計と呼びます。地球上のほとんど全ての生物が概日時計を持ち、明暗や温度といった環境サイクルが完全にない状況でも、約24時間周期のリズムが見られるそうです。そして、このリズムが存在するのは、各細胞の中で時計遺伝子が「時」を計っているためだということでした。また、多くの人は24時間よりも長い周期のリズムを持っているため、夜型の人が多いそうです。さらに、若い人ほど朝型が少なく、必要な睡眠時間が長いことが知られているとのことでした。なお、海外の研究では、ある高校において、半分のグループの始業時間を1時間遅らせたところ、従来の始業時間のグループよりも、偏差値が有意に向上したという結果が得られたとお話ししました。
参加者との質疑応答では、「体内時計の乱れをなおすのに効果的な方法は何ですか。」という質問に対して、「平日は朝型で、休日は夜型になってしまう方は多いかと思いますが、これは一週間に一度時差ボケを繰り返すことになって、体内時計の乱れにつながることになります。これを防ぐには、一番望ましいのは休日でも就寝時間と起床時間を一定にすることです。」といったやりとりがありました。
アンケートでは、「自分は中学生で、体内時計というワードしか聞いたことしかなかったのですが、とても分かりやすく、面白かったです。」といった御意見が数多く寄せられました。

吉種 光プロジェクトリーダー
 第6回都医学研都民講座 - 11月24日開催 - レビー小体型認知症を
第6回都医学研都民講座 - 11月24日開催 - レビー小体型認知症を2021/11/24 開催

第6回都医学研都民講座 オンライン開催
11月 24日(水曜日)、当研究所では、「レビー小体型認知症をめぐる最近の動向」と題して、第6回都医学研都民講座をオンライン方式で開催しました。今回は、都立松沢病院精神科・脳神経内科医長の西尾慶之先生を講師にお迎えしました。
西尾先生からは、「レビー小体型認知症を通してみる脳・こころ・身体」と題してお話しいただきました。レビー小体型認知症は、アルツハイマー病の次に患者数が多いとされる認知症の原因疾患です。アルツハイマー病では、記憶障害等の認知障害が主な症状になりますが、レビー小体型認知症では、幻視や妄想等の精神症状、動作緩慢等の運動症状、便秘等の自律神経症状というように多彩な症状を特徴とするそうです。また、診察の場で幻視の状況を確認することが難しいため、かつてパレイドリア・テストと呼ばれる幻視もどきの錯視を見つけるツールを開発したとのことでした。パレイドリアとは、壁のしみや雲の形等が人や動物に見える心理的な現象ですが、このパレイドリア・テストは、国際的にもガイドラインとして認められており、直接的に幻視と類似する症状を誘発することで、正確な診断に役立てるものだそうです。なお、幻視が現れる原因としては、視覚中枢のある後頭葉が障害されるためであり、その結果、視覚認知障害が現れやすくなると考えられる、とお話しいただきました。
講演後のアンケートでは、「調剤薬局勤務薬剤師ですが、レビー小体型認知症の専門家の先生に詳しくお話を聞くのは、初めての機会で、とても分かりやすく、ためになりました。薬局に訪れる患者様でもレビー小体型認知症と思われる方が、時々いらっしゃるので、患者様やご家族の気持ち、治療方針を理解する上で大変ためになりました。」「レビー小体型認知症の母を介護しています。今後、患者に起こること、医師が何を診てレビー小体型認知症と診断したのか理解できました。症状が日内変動すること、認知機能が保たれている部分も多いことから、なかなか周囲の理解が得られず、サポートを受けることに苦心しています。今回の講座は非常に分かりやすく、今後、サポートを受けていくために何を伝えたらよいのか、患者の状態をどう伝えたら良いのかを考える良い機会になりました。」といった御意見を多く頂きました。

西尾慶之先生
 第5回都医学研都民講座 - 10月21日開催 - 病原体の感染のしくみ
第5回都医学研都民講座 - 10月21日開催 - 病原体の感染のしくみ10月 21日(木曜日)、当研究所では、「病原体の感染のしくみ ‐新型コロナウイルスとクラミジアを例に‐」と題して、2021年度第5回都医学研都民講座をオンライン方式で開催しました。今回は、国立感染症研究所品質保証・管理部主任研究官の花田賢太郎先生を講師にお迎えしました。
まず、当研究所細胞膜研究室の笠原浩二室長から、「新型コロナウイルスなどの病原体の感染のしくみ」と題してお話ししました。感染症とは、ウイルスや細菌等の病原体が、生体の防御壁を突破し、体内で増殖して不具合を起こすことです。この防御壁として、皮膚や粘膜による物理的な防御、元々備わっている自然免疫と、一度侵入した病原体の情報を記憶し、再び侵入してきた際に攻撃する獲得免疫の3つが挙げられると説明しました。そして、新型コロナウイルスが感染する仕組みとして、ヒトの細胞膜にある、本来、血圧の調節を行う酵素であるアンジオテンシン変換酵素2と、ウイルスの表面のスパイクタンパク質と呼ばれる突起にある受容体結合領域が結合して行われるとお話ししました。
続いて、花田先生から、「ヒト細胞の作る脂質を病原体が盗み取る仕組み:クラミジアによるセラミド輸送タンパク質ハイジャックを例に」と題してお話しいただきました。脂質は細胞の膜を構成する主な成分で、全ての細胞にとってなくてはならないものです。細胞の中では、様々なミトコンドリア等の細胞内小器官に振り分けられながら脂質が合成されますが、長らくそのメカニズムは不明だったそうです。そのような中で先生のグループは、脂質の一種であるセラミドを細胞内において輸送するタンパク質を発見したとのことでした。また、このタンパク質が欠損した細胞では、病原体のクラミジアに感染しても菌が増えませんが、この仕組みを調べたところ、クラミジアは、このタンパク質を乗っ取ることで、ヒト細胞が合成したセラミドを盗み取り、クラミジアの増殖に役立てている仕組みを明らかにしたとお話しいただきました。
講演後の質疑応答では、数多くの質問をいただき、所定の時間を終えた後も、花田先生には希望者に対して質問に答えていただきました。

笠原室長
 第4回都医学研都民講座 - 9月5日開催 - 痛みなくがん治療を受けるコツ
第4回都医学研都民講座 - 9月5日開催 - 痛みなくがん治療を受けるコツ
2021/9/5 開催

第4回都医学研都民講座 オンライン開催

池田和隆分野長
9 月5日(日曜日)、公益財団法人東京都医学総合研究所では、「痛みなくがん治療を受けるコツ」と題して、2021年度第4回都医学研都民講座をオンライン方式で開催しました。今回は、東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部部長の住谷昌彦先生を講師にお迎えしました。
まず、当研究所精神行動医学研究分野の池田和隆分野長から、「痛みに効く薬の基礎知識」と題してお話ししました。痛みは生体警告システムとして重要ですが、痛みが過度になると、不快感が増し、QOLは低下し、さらに免疫力も低下してしまうとのことでした。このため、痛みを適切に抑えることも重要ですが、痛みに対応するには、個々人に適した鎮痛薬を適量で使う必要があります。これは同量の鎮痛薬を処方しても、遺伝要因や環境要因のため、ある人には良く効いても、他の人の場合には、鎮痛が不十分だったり、また、別の人の場合には強い副作用が現れたりといった形で、個人によって効き方が異なるためであるとお話ししました。

住谷昌彦先生
続いて、住谷先生から、「元気に、痛みなくがん治療を受けるコツ」と題してお話しいただきました。緩和ケアでは、患者とその家族のQOLに関わる痛みや、その他の身体的・心理社会的な問題を早期に見つけ対応することが重要で、また、苦痛が強くなる前に苦痛が現れないように予防することが望ましいとのことでした。実際、苦痛の緩和のため早期から緩和ケアを受け、医療用麻薬を使用した場合、緩和ケアを受けず、医療用麻薬を使用しない場合と比べ、がんで亡くなるリスクが低下するそうです。また、がんに罹った場合、筋肉量の低下が往々にして起こりますが、この低下が治療の不成功や副作用の増強に関連することが、最近の研究で判明してきているそうです。このため、積極的に運動療法を取り入れることで、身体機能やQOL等が改善するとのことでした。さらに、肥満の場合、手術後の合併症の発症が多く、痛みの観点からも、手術後の傷の痛み、化学療法後の手足の痛みや痺れ、腰痛を悪化させるため、適正体重の維持が重要であるとお話しいただきました。なお、この肥満が痛みを悪化させるメカニズムについては、先生の研究グループが、脂肪から痛みを悪化させる物質が出ているためであることを解明したそうです。
講演後のアンケートでは、「保険薬局薬剤師として参加しました。肥満と痛みの関係、鎮痛早期介入によりがん治療効果・延命に影響することについてのお話しが、とてもためになりました。」といった御意見を多く頂きました。
 第11回都医学研シンポジウム - 8月18日開催 - 病いは物語である
第11回都医学研シンポジウム - 8月18日開催 - 病いは物語である
2021/8/18 開催

第11回都医学研シンポジウム オンライン開催
8 月18日(水曜日)、公益財団法人東京都医学総合研究所では、第11回都医学研シンポジウム「病いは物語である」を、オンライン方式で開催しました。

医者仲間からときどき聞かれることがある。「狭心症が心臓の病気で、気管支ぜんそくが肺の病気であるように、精神疾患は脳の病気ですよね」と。まったくもってそのとおりと肯定することが難しいのは、そこに屈託なき誤解の余地が立ち込めるからだ。(糸川の講演要旨より)
2010年頃のことだったと思います。精神病症状を経験された方たちに研究へ協力をお願いするために、いくつもの病院を訪ねていた時のことでした。たまたま、江口先生が勤務されていた病院に伺うことがあって、求められて医局で研究の説明をさせていただきました。脳の研究者の話すことですから、きわめて物理化学的な内容を、どこまでも細部の厳密性に拘って述べた気がいたします。話が進むにつれて、皆さんの表情に微妙な困惑が広まったことを覚えています。江口先生は御高名な先生でしたから、その場にいらっしゃるのはすぐにわかりましたが、ご挨拶ぐらいで立ち入ったお話しはしなかったと思います。

憑依は精神病理であるにとどまらず,模倣や変身というより多様な現象に結びついている。さらにかつて世界の各地で流行現象として有名になった集団憑依に対して,エスキロールやシャルコーやジャネといった近代精神医学や神経学,心理学の創始者たちはその背景に「模倣の力」があることを十分理解していたことが分かる。(江口重幸先生の講演要旨より)
それから、10年近くたった最近のことです。北中先生が主催された慶應義塾大学での研究会で、江口先生と私はディスカッサントとして招かれ再会しました。江口先生の病院であれほどモノと細部しか述べなかったはずの私が、打って変わってコトと全体ばかりを発言したからでしょうか。研究会場から駅までの帰り道、たぶん10分程度だったと思われますが、江口先生と私は互いに息継ぎを忘れるほど夢中になってモノとコトについて語り合いました。
全体は部分の集合であること、上位によって下位は制御され、それら全てが数学的に関係しあう。このモノの三原則こそが近代科学であり、だから科学が心を探求するとき、脳というモノの法則がミクロな細部として立ち現れるのです。あくまで、心がモノならばという前提のもとで。

シャーマニズムが「民俗的文化リソース」として機能することで、現代の苦悩をマネージすることに役立っていることであり、そのとき現代の都市文化とシャーマニズムが混淆していくことであった。(東畑開人先生の講演要旨より)
コトとの出会いをさかのぼると、幼いころに過ごした実家の近くにあった、新宿の高層ビルが建つ前の浄水場跡にたどり着きます。大都会の真ん中に忽然とひらけた無造作な原っぱ。元旦の朝そこを一人で訪れることが好きでした。今から考えてみれば、無人の大都会の研ぎ澄まされた朝だけに許された、モノの三原則から全く解き放たれた時空を楽しんだのだと思います。
グローバル都市で臨床と霊を語る東畑先生の実践的なお話しに引き込まれていったのには、個人的な理由もありました。「都市文化とシャーマニズム」と伺って思い出したことがあったからです。2017年7月に、シャーマニズムの調査で沖縄と宮古島を訪ねた時のことでした。ユタとかカンカカリャと呼ばれたシャーマンの方たちとお話ししていて、幼い頃そっと立ち臨んだ浄水場跡の、あの清冽な朝を感じたからです。

いまや地球環境と人類社会の持続可能性は大きく脅かされ、その克服が喫緊の課題となっている。そのために人間/自然(精神/物質)の区分にもとづいて対象を「モノ」とみなす近代的自然観から脱却し、「コト」の連鎖のうちに人間と自然を捉えるエコロジー的自然=人間観が提唱され、反響を呼んでいる。(村澤真保呂先生の講演要旨より)
近代神経科学は、心が頭蓋骨の内側に局在するという前提のもとで発展してきました。ドーパミンやセロトニンが活発に増減して、海馬や側坐核に電気的シグナルが飛び交う。近代科学の描く心は、まるでモビルスーツの操縦席に座るホムンクルスのようです。座禅をしてみれば分かります。頭蓋骨の内側にしかなかったはずの自分が、半跏趺坐を組んだ踵から法界定印を重ねた指先まで自分になってゆくのを。さらに、その指先の先へ、足の外側のさらに外へと、ホムンクルスは蒸発するように広がり続けます。村澤先生がかつて日本各地で見られた狐憑きが、都市開発で里山が失われるにつれ減っていったとお話しされました。頭蓋骨で操縦かんを握るホムンクルスに、心が完結しないからだと思います。

AIが共感することの意味、その構造を考えることは、私たちにとっての「共感」の難しさ、危うさに思いを馳せることでもある。(北中淳子先生の講演より)
講演後、村澤先生から「コトが原因で器質的モノに影響が出ることがあるのでは」と御質問をいただきました。宗教的恍惚から手足にスティグマを生じた症例マドレーヌだけでなく、トラウマを経験した被害者のMRI画像で側頭葉や海馬の容積が小さいように、コトからモノへの作用は十分にあると思います。もちろん、その逆のモノからコトも。北中先生がお話になった、中国版twitterに残された遺言的メッセージがオランダのAI自殺予防プログラムによって発見され、中国のボランティアが連携して、遺言を残した人物を自殺前に救助した例もありました。つまり、デジタルとAIテクノロジーというモノが、自殺防止というコトに向かう作用です。
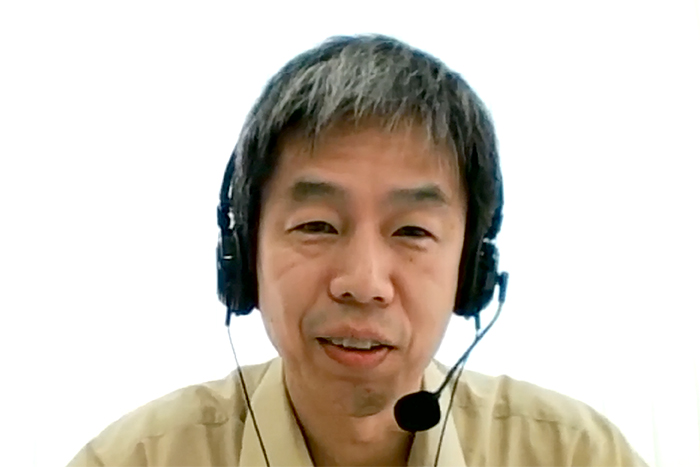
もちろん薬物療法も行うが、むしろ、本人や多職種チームが一緒になって試行錯誤をしながら、本人が住みやすい環境を一緒に作り上げていく息の長いプロセスであると言った方が適切である。(野口正行先生の講演要旨より)
意味や価値というコトが物語として紡がれたとき、関わった人々の共鳴を経て人を動かす力を得ることもあります。野口先生は地域で様々な困難をかかえる当事者の方を支援するお話しのなかで、その方の個人史に支援者が腑に落ちる理由を発見して、当事者の方を安全で安らぐ環境へつながれた事例を示されました。
5時間にも及ぶオンライン・シンポジウムは、終盤の総合討論でシンポジストそれぞれの想いが尽きることなく往来し、まるでステージがあるかのようなそこに、不思議な高揚感を帯びた清冽なコトが降り立ちました。私の専門ではそれを正確に表現できる用語がありませんが、舞い降りたそれを霊と呼んだ人がいたとしても、あの場の誰も否定はしなかっただろうと思います。 (糸川昌成:東京都医学総合研究所 副所長)
(糸川昌成:東京都医学総合研究所 副所長)
 第37回サイエンスカフェin上北沢 - 8月7日開催 - ゲノム配列を、みる
第37回サイエンスカフェin上北沢 - 8月7日開催 - ゲノム配列を、みる
2021/8/7 開催

第37回 サイエンスカフェ in 上北沢 オンライン開催
8 月7日(土曜日)、公益財団法人東京都医学総合研究所では、第37回サイエンスカフェin上北沢「ゲノム配列を、みる」を、ゲノム医学研究センターの川路 英哉副センター長を話題提供者として、オンライン方式で開催しました。
今回のサイエンスカフェは、ゲノムの配列がどのようになっているのかを実際に見てもらうため、ゲノムDNAの塩基配列、すなわち、アデニン、チミン、グアニン及びシトシンの4種類の塩基が一列に並んでいる様子を見ることができ、インターネットで公開されているデータベースを使って体験していただきました。使用したのは、川路副センター長がその運営にも関わっている、カリフォルニア大学サンタクルーズ校のUCSCゲノムブラウザ・データベース(https://genome-asia.ucsc.edu/)でした。
まず、ヒトの体の中にはゲノムがあって、そのゲノムがRNAにコピーされ、タンパク質ができますが、そのRNAを作っているところを遺伝子と呼ぶこと、そして、その遺伝子はゲノムDNA上にあり、ごくわずかしかないことなどを説明しました。また、ヒトの体の細胞は37兆個もあるとされ、細胞の種類によって必要な遺伝子等が異なることから、DNA配列が解読されても理解できていないことが多いそうです。このため、日夜、遺伝子はどうやって細胞ごとに機能を切り替えているのか、遺伝子でない部分は本当に必要なのか、といったことを研究しているとお話ししました。その後、データベースの操作方法等を説明した後、参加者のみなさんがそれぞれ自由にデータベースを操作しました。
アンケートでは、「自分の将来の夢は研究者ですが、まだ何を研究したいかが決まっていないので、遺伝子の分野を知ることができるとても良い機会になりました。」「研究者の方々が実際に使っているデータベースを見ることが出来て非常に面白かったです。大学で遺伝やゲノム編集といった分野を学びたいと思っていたので、今日のサイエンスカフェを通して、よりその思いが強くなりました。」といった御意見が数多く寄せられました。

お話をする川路センター長
 都民講座
都民講座 7 月10日(土曜日)、当研究所では、「ポリオ根絶の戦い ‐人類はウイルスを根絶できるのか?‐」と題して、2021年度第3回都医学研都民講座をオンライン方式で開催しました。今回は、国立感染症研究所ウイルス第二部主任研究官の清水博之先生を講師にお迎えしました。
まず、清水先生から、「世界ポリオ根絶計画の現状と残された課題」と題してお話しいただきました。ポリオは小児麻痺とも呼ばれ、かつて日本においては、1950年代から流行し始め、その際、不活化ワクチンの研究が進んできていたものの、1960年に発生した大流行には間に合わず、旧ソ連やカナダから未承認の生ワクチンを緊急輸入し、その結果、感染者が激減したとのことでした。その後、WHOが1988年に世界ポリオ根絶計画を策定し、対策を進めた結果、野生株ポリオの流行国は、現在ではアフガニスタンとパキスタンの2ヶ国のみになったそうです。また、ポリオがWHOの根絶計画に数ある感染症の中から選ばれた理由として、重篤な疾患の大規模な流行があったこと、自然宿主はヒトのみであること、有効で安価なワクチンが存在したことが挙げられる、とお話しいただきました。
続いて、当研究所ウイルス感染プロジェクトの小池智プロジェクトリーダーから、「ポリオ後の新たなエンテロウイルス感染症」と題してお話ししました。世界ポリオ根絶計画の進捗によりポリオの発生は抑えられてきたものの、近年、ポリオウイルスと近縁のエンテロウイルスA71やエンテロウイルスD68等の流行が発生しているそうです。エンテロウイルスA71は手足口病の原因となるウイルスとして知られていますが、これらのウイルスに感染すると、稀に中枢神経系にウイルスが入ってしまうことがあり、この場合には麻痺等を起こしてしまうとのことでした。また、ウイルス感染症の蔓延を防ぐため、毒力の強いウイルスが出現していないかといった流行状況の把握と、ワクチンや抗ウイルス薬の開発を目的に研究を進めているとお話ししました。
講演後のアンケートでは、「ポリオ及び関連ウイルスに対するワクチン開発の経緯がよく理解できました。」といった御意見を多く頂きました。

左から、清水博之先生、小池智プロジェクトリーダー
 都民講座 - 6月5日開催 - 限界突破を実現する
都民講座 - 6月5日開催 - 限界突破を実現する2021/6/5 開催

第2回都医学研都民講座 オンライン開催
6 月5日(土曜日)、当研究所では、「限界突破を実現するテクノロジー」と題して、第2回都医学研都民講座をオンライン方式で開催しました。今回は、ソニーコンピュータサイエンス研究所リサーチャー・プログラムマネージャーの古屋晋一先生を講師にお迎えしました。
まず、当研究所脳機能再建プロジェクトの田添歳樹主席研究員から、「人工神経接続の技術による脊髄損傷者の随意運動の再獲得」と題してお話ししました。脊髄損傷等により身体麻痺を引き起こした場合、動かすのが難しくなった手足で反復運動を行い、少しずつ元の運動機能を取り戻していきますが、麻痺が重度になると、そもそも運動を行うこと自体が困難になります。そして、この状況を克服するため、脊髄損傷者が自らの意思で麻痺した両足を動かすことができるように、人工神経接続という技術を用いて研究しているとのことでした。ある事例では、損傷した脊髄を人工神経となるコンピューターを介して迂回し、脳から手に伝わった運動の信号を、下肢の筋肉を支配している腰髄に伝えることで、動かすことのできなかった足を動かすことができるようになったとお話ししました。
続いて、古屋先生から、「神経科学とロボティクスによる音楽家のスキルの限界突破」と題してお話しいただきました。演奏家の多くは、幼少期から膨大な練習を経て、卓越したスキルを獲得していますが、最近の研究では、この獲得の割合において、練習量、つまり努力の量の結果といえるのは4割程度に過ぎないといわれているとのことでした。また、練習を重ねた結果、脳が変わりにくい状態になってしまい、かえって努力だけでは限界を突破することができなくなるそうです。このため、先生は、演奏家やその卵である若者に対して、限界を突破するため、脳と身体の動作原理やロボティクスに基づいたトレーニングを行っているそうです。例えば、ジュニア向けのアカデミープログラムでは、演奏家によるレッスンや音楽理論等の講義といった芸術教育と、先生たち研究者によるスキル診断や身体に関するコーチング等の身体教育を行っていると、お話しいただきました。
講演後のアンケートでは、「田添先生のお話をうかがって、脊髄損傷の患者さんにとって希望が持てるお話で、今後の研究に注目したいです。」「古屋先生のお話で、スポーツのように音楽の分野でも科学を取り入れた練習法がひろがって、「創造性の限界を突破できる社会」になる未来を想像するとワクワクします。」といった御意見を多く頂きました。

左から、古屋晋一先生、田添研究員、西村脳機能再建プロジェクトリーダー
 都民講座 - 4月30日開催 - ゲノム研究がもたらす
都民講座 - 4月30日開催 - ゲノム研究がもたらす2021/4/30 開催

第1回都医学研都民講座 オンライン開催
4 月30日(金曜日)、当研究所では、「ゲノム研究がもたらす新しいがん医療」と題して、第1回都医学研都民講座をオンライン方式で開催しました。今回は、九州大学大学院薬学研究院医薬細胞生化学分野教授の藤田雅俊先生を講師にお迎えしました。
まず、当研究所の正井久雄所長から、「ゲノムと私たちの生活」と題してお話ししました。がんは、ゲノムに傷が蓄積することにより発生します。ゲノムの傷は、傷をつける物質に触れること、あるいは、遺伝的に傷つきやすい性質を持っていること、も原因になりますが、細胞が増殖する際のDNA複製または染色体分配などのステップの失敗により、長い間に自然に傷がたまっていくことが最も多い原因であることがわかったとのことでした。
続いて、当研究所ゲノム動態プロジェクトの笹沼博之副参事研究員から、「がん撲滅に向けたがんゲノム研究の現状:乳がんを例に」と題してお話ししました。がんゲノム解析が進んだ結果、がん細胞が共通に持つ遺伝子変異が判明し、特にp53という遺伝子は様々ながんで変異が見られます。また、これからのゲノム医学研究では、多くの患者の血液等のがんゲノムを自動解析し、公開データベースに保管し、世界中の研究者がこのビッグデータを利用して、新たな診断、治療法を導き出すシステムが広がると考えられます。さらに、各人の遺伝子型による、薬や治療法への応答の違いのメカニズムが明らかになり、将来は個人のゲノム情報に基づく最適な治療法をコンピューターが提示できるようになるとのことでした。
最後に、藤田先生から、「ゲノム研究から明らかになった発がんの仕組みとそれを利用した新しいがん治療法の開発」と題してお話しいただきました。生体内での細胞増殖は厳密かつ適切に制御されていますが、ある種の遺伝子では、変異が起きた結果、細胞が増殖し続け、がん細胞が発生します。そして、この遺伝子変異を網羅的に調べ、変異したタンパク質に対する阻害剤や、形を元に戻す化合物を発見して治療に用いる治療法ががんゲノム医療であるとお話しいただきました。
講演後のアンケートでは、「ゲノムというと難しいイメージがありましたが、先生方のお話は分かりやすく、夢中で聞き入りました。もっと気軽に遺伝子検査ができたり、ゲノム検査が標準治療になる日が来ると良いと思いました。」といった御意見を多く頂きました。

左から笹沼研究員、藤田雅俊先生、正井所長
