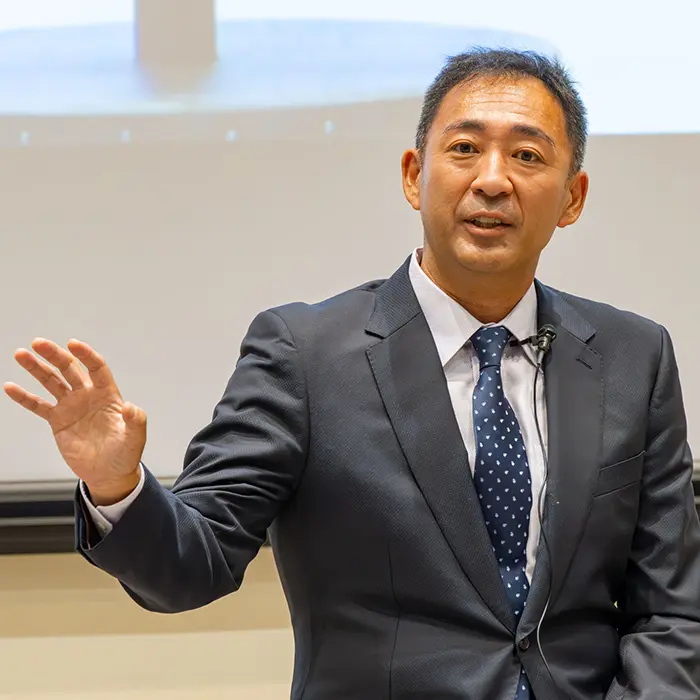脳神経回路形成プロジェクト隈元 拓馬
7月18日、「自閉スペクトラム症につながる脳発達過程を理解する~脳発生とロボティクス研究から探る脳の形づくりと機能発達~」と題して、2024 年度第 3 回の都民講座を開催しました。今回の試みとして、自閉スペクトラム症に関し異なるアプローチで研究を進めている二人の講師、東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構の長井志江特任教授と群馬大学大学院医学系研究科遺伝発達行動学の三好悟一教授にご講演をお願いし、講演の最後にはご聴講の皆様からのご質問に対して対談方式を取りながら、異なるアプローチからどう問題に対応していけるのかについてお話しいただきました。長井先生のご専門はロボティクスで、「脳の予測情報処理に基づく認知発達と発達障害」のタイトルでご講演いただきました。人間の脳の基本的機能とされる予測符号化*1 に基づき,発達障害の発生原理を計算論的アプローチから明らかにしようという取り組みや、実際に自閉症患者からはどのように世界が見えているのかを、視覚体験シミュレータを作成し健常者でも体験できるという試みなど、最先端のアプローチをご紹介いただきました。三好先生のご専門は神経発生生物学で、「自閉スペクトラム症につながる脳発達過程を理解する」のタイトルで、自閉スペクトラム症の原因遺伝子の一つである転写因子 Foxg1 に着目し、遺伝子改変マウスモデルを用いたお仕事を紹介いただきました。1つの遺伝子のわずかな変異や量の差異で、異なる自閉スペクトラム症様症状を呈することが興味深く、三好先生のご研究が今後どのようにヒトの疾患の原因解明へと繋がっていくのか、ご参加の方々にも大変興味を持っていただいた様子でした。今回は、対面で 29 名、オンラインで 147 名と多くの方にご参加いただき、改めて自閉スペクトラム症に対する都民の皆様の関心の高さが伺えました。今回のように最先端の基礎研究には様々なアプローチがあり、日本の研究者も大きく寄与しています。このような研究活動をより多くの都民の皆様に今後も紹介していく予定です。今回ご参加いただいた皆様、演者の先生方に深く御礼を申し上げます。ありがとうございました。
*1 環境から感覚器を通してボトムアップに入力される信号と、脳が過去の経験や知識、また他の感覚からの信号をもとに、内部モデルを通してトップダウンに予測する信号の誤差を最小化するように、情報処理を行う仕組み